
「障がい者雇用でアバターって、本当にそんな事例が存在するの?」
「アバターで働くってどういう仕組み?現場ではどう活用されているの?」
「うちの会社でも導入できるのか、具体的なイメージが知りたい」
障がい者雇用におけるアバター就労に興味がある企業担当者の中には、興味はあってもイメージできないという方が多いのではないでしょうか。
結論からいうと、アバター(分身のようなキャラクター)を活用した障がい者雇用の取り組みは、すでに複数の企業や現場で実用化されており、法定雇用率の達成や新しい戦力の確保につながる現実的な手段のひとつとなっています。
 この記事では、アバターを活用した障がい者雇用の最新事例を紹介しながら、導入メリットや向いている業種、始め方のステップまでを具体的に解説します。
この記事では、アバターを活用した障がい者雇用の最新事例を紹介しながら、導入メリットや向いている業種、始め方のステップまでを具体的に解説します。
読み終える頃には、「うちの会社ではこの方法が合いそうだ」「こうすれば障がいのある方にも働いてもらえるかもしれない」といった、自社での活用イメージを具体的に描けるようになっているはずです。
ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 障がい者雇用でアバターを活用した事例

近年、アバター(分身のようなキャラクター)を通して障がい者に働いてもらうという取り組みが昨今注目されています。
しかしながら、「障がい者雇用にアバターって実際どうなの?」「本当にそんな働き方があるの?」「どうやって現場で働いてもらうの?」など、上手くイメージできないという方が多いのではないでしょうか。
ここでは実際に企業が取り組んでいる3つの代表的な事例をご紹介します。
障がい者雇用でアバターを活用した事例 |
いずれも、通勤や対面業務が難しい障がい者が、アバターを操作することによって従事している事例です。
どのような働き方を実現しているか見ていきましょう。
1-1. コンビニの遠隔接客で障がい者を雇用している事例(ナチュラルローソン)
障がい者雇用におけるアバター活用の事例としては、ローソンの取り組みが最も広く知られており、企業にとっても先行事例として参考にされることが多い代表的な存在です。
この取り組みは、アバター遠隔接客システム「AVACOM」を提供するAVITA株式会社との共同プロジェクトとして進められており、技術面・運用面の両面で連携が図られています。
AVACOMは、画面上のアバターを介して遠隔地のオペレーターがリアルタイムで接客できる仕組みで、ローソンではその柔軟な設計を活かし、障がいのある方が自宅から複数店舗に対応できる形での雇用を模索しています。
 ローソンでは、東京都内に開設した近未来型店舗「グリーンローソン」で、アバターによる接客サービスを試験導入しています。
ローソンでは、東京都内に開設した近未来型店舗「グリーンローソン」で、アバターによる接客サービスを試験導入しています。
このアバターは、画面上に表示されるアニメ調のキャラクターで、遠隔地にいる人間がリアルタイムで音声と操作を担当しています。
この仕組みにより、通勤が難しい人や対面業務に不安のある人でも在宅で接客が可能になります。
実際にアバターオペレーターに採用された石平由希さん(仮名)は、筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群(ME/CFS)という難病を抱え、これまで安定して働くことができなかった方です。
石平さんは、「当日の体調が読めず朝起き上がれない日もある」と語る一方で、「前例がなければ、自分が壊していけばいい」という前向きな思いからアバター接客に挑戦しています。
操作は、パソコンのカメラで自身の動きを読み取り、アバターにリアルタイムで反映させる形式です。
声も変換されるため、外見や性別に左右されずキャラクターになりきって接客ができます。
体調の波がある方でも、自宅から無理なく働ける設計となっており、本人にとっても大きな希望となっています。
ローソンによると、アバターオペレーターを一般募集したところ全国から400名近い応募があり、書類選考・面接を経て30名程度を採用したそうです。
2025年度には1,000名のオペレーター認定を目指しているとのことです。
ローソンのアバター接客モデルは、障がいのある人にとって新しい職域を開拓するだけでなく、企業側にとっても人手不足対策や法定雇用率の達成に貢献する事例といえるでしょう。
参考:TBS NEWS DIG「アバター店員が接客 ローソンが近未来型店舗オープン~ハンデや場所にとらわれない新しい働き方とは~」
1-2. テーブル上の分身ロボットを通して障がい者が接客を行う事例(OriHimeカフェ)
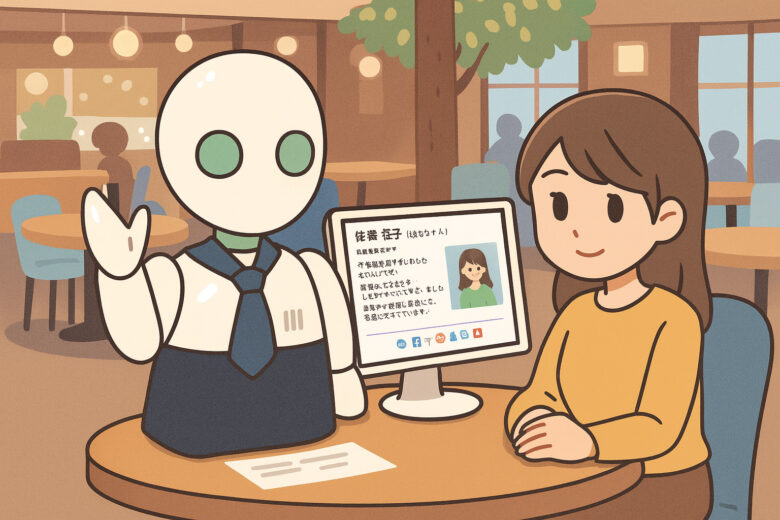
画面に表示されるアバターとは異なり、テーブル上に設置された実体あるロボットを通じて接客を行うスタイルとして知られているのが、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」を活用した取り組みです。
この事例は、複数の場所での実証実験を経て、現在は分身ロボットカフェ「DAWN ver.β」(東京都・日本橋)で常設実験中であり、現場ではすでに障がいのある方による実用的な就労支援の形として定着しつつあります。
分身ロボット「OriHime」を操作する障がい者は「パイロット」と呼ばれており、多くは肢体不自由や難病などで外出が難しい方々です。
自宅などからパソコンやタブレットを使って遠隔操作し、来店したお客様へのあいさつやメニュー説明を行います。
ロボットが視線や指の動きで操作できる設計となっており、声かけや表情・動作もリアルタイムに伝えることができるため、自然なコミュニケーションが可能です。
パイロットの中には、ほとんど寝たきりという障がい者も含まれています。
分身ロボットを使った就労モデルは、障がい者本人の働く意欲を引き出すだけでなく、社会との接点を築く実践的な方法として注目されています。
参考:TRY ANGLE EHIME公式note「顧客満足度90%以上、障がい者支援アバターロボット導入成果【えひめロボティクス障がい者サポートコンソーシアム| 実装報告】」/分身ロボットカフェ DAWN ver.β公式サイト
1-3. メタバース空間に再現した仮想オフィスで障がい者が勤務する事例(Man to Man Animo株式会社)

リモート接客や分身ロボットとは異なる切り口として、メタバース空間を活用した仮想オフィスの事例も注目されています。
メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間のことです。
利用者は自分の分身である「アバター」を使い、他者とコミュニケーションを取ったり、会議や業務に参加したりすることができます。
近年ではこの技術を活用し、物理的に出社が難しい障がい者の方が「仮想オフィス」にログインして業務を行う事例が増えてきています。
Man to Man Animo株式会社では、重度の身体障がい(SMA:脊髄性筋萎縮症)がある新卒社員をエンジニアとして採用し、完全在宅での勤務体制を構築しています。
実際の業務では、バーチャルオフィスツール「ovice(オヴィス)」を導入し、在宅勤務でもリアルタイムで雑談や相談ができる空間を仮想的に再現しています。
この仮想空間では、同僚とアバターを通じて雑談したり、必要に応じて隣席に移動して話しかけたりと、まるで実際のオフィスに出社しているかのような感覚で働くことができます。
従来の在宅勤務で課題とされてきた「つながりの希薄さ」や「気軽なコミュニケーションの難しさ」を大きく改善できたといいます。
このような取り組みは、出社が困難な障がい者の就労手段として非常に実用的であると同時に、企業にとってもチーム体制を維持しつつ柔軟な雇用を実現する有効な手段といえるでしょう。
※この事例では、画面にアバターを表示しているかどうかは明示されていないものの、ユーザーの存在を仮想空間上に「アイコン」として表示して他者と近づいたり会話したりできる仕組みが備わっています。そのため、本記事では「アバター的な働き方の一例」として紹介しています。 |
参考:Flexible Synergy Lab「働き方事例シリーズvol.7「障がい者雇用」~フレキシブルな働き方が人生の選択を増やす~」
2. 障がい者雇用でアバターを活用するメリット

アバター(分身のようなキャラクター)を活用した障がい者雇用の取り組みはまだ新しい試みではありますが、1章で解説したように、すでにいくつかの事例が現れ始めています。
こうした取り組みが注目されている背景には、企業・障がい者の双方にとって多くのメリットがあるからです。
ここでは、実際にアバターを使った雇用のどのような点が評価されているのか、企業側の視点を中心に整理してご紹介します。
とくに、法定雇用率の達成、人材不足の補完、働きやすい環境の整備といった観点から、アバターの活用がどのような効果をもたらすのかを具体的に見ていきましょう。
2-1. 法定雇用率の達成に向けた現実的な選択肢になる
障がい者雇用にアバターを活用することは、法定雇用率の達成に向けた有効な選択肢になるというメリットがあります。
2024年4月から民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられ、さらに2026年7月には2.7%まで段階的に引き上げられる予定です。
従業員規模によっては新たに障がい者の採用義務が生じる企業もあり、採用・配置の体制を見直す必要に迫られるケースもあるでしょう。
しかし実際には、「どのような職種で、どのように働いてもらうか」が具体化できずに雇用が進まない企業も多く見られます。
そのような中、アバター接客やメタバース空間などを活用した在宅型の就労は、物理的な職場環境の整備が難しい企業でも導入しやすい手段といえます。
2-2. 通勤や対面が難しい障がい者に無理なく働ける就労機会を提供できる
アバター接客や仮想空間での勤務は、障がいのある方にとっても「無理なく働ける選択肢」となります。
たとえば、通勤に身体的な負担がかかる方や、対面でのコミュニケーションに不安を抱える方、体調に波がある方などは、従来の職場環境では安定的に働くことが困難でした。
アバターを介した接客や、メタバース空間での業務なら、場所や見た目にとらわれず、自分のペースで働くことができます。
また、在宅勤務であっても「職場の一員」として他の社員と自然に関われることから、社会参加の実感を得やすい点も重要です。
2-3. 新たな人材の活用で「現場の人手不足」を解決できる
アバターを活用することで、これまで就労が難しいとされていた方々に新たな働く機会を提供できるようになります。
障がいのある方にとっては、通勤や対面コミュニケーションといった物理的・心理的なハードルを避けながら働ける環境を整えることができ、これまで十分に発揮されてこなかった力を業務に活かすことが可能になります。
そしてこの仕組みは、障がいのある方に限らず、たとえば育児中で外に働きに出られない方、地方や海外に在住していて都市部の職場に通えない方など、幅広い人材にも共通するメリットをもたらします。
実際、ローソンによるアバター接客の事例では、難病を抱える方とともに、シニアの方や子育て中の方、海外在住の日本人など、さまざまな人材を活用しています。
企業側にとっては、こうした「今までリーチできていなかった人材」に業務を担ってもらえることで、人手不足の解消につながります。アバター接客をきっかけに働く人の選択肢が広がれば、組織全体にとって大きなメリットをもたらすはずです。
3. 障がい者雇用でのアバター活用が向いている業種・企業の例

ここまでの内容を踏まえたうえで、とくにアバター(分身のようなキャラクター)を活用した障がい者雇用が向いている業種・企業の例を、アバターの形式ごとにまとめました。
3-1. 画面に表示されたアバターが接客する形式:コンビニや弁当店などと相性が良い
画面に表示されたアバターを通じて、遠隔地にいるオペレーターがリアルタイムで接客を行う形式は、コンビニやスーパー、弁当店、土産物店などの対面販売を行う店舗に特に向いています。
とくに、セルフレジや無人レジを導入している店舗では、店頭にスタッフが常駐していない時間帯や少人数で運営している場面も多く、「接客の質を維持しながら人件費を抑えたい」というニーズがあります。
そうした環境で、アバター接客は最小限の導入スペースと通信環境で対応でき、セルフレジの近くや店舗入口などに小型ディスプレイを設置するだけで運用が可能です。
このような、簡易な接客・案内・商品説明などを必要とする店舗では、障がいのある方が画面のアバター越しに遠隔接客するというスタイルが適しているといえるでしょう。
3-2. アバターロボットを使って接客する形式:カフェや観光施設などの交流重視の場所に適している
アバターロボット(分身ロボット)を実際のテーブル上に設置して、遠隔地にいるオペレーターが操作する形式は、カフェや観光案内所、イベントスペースなど、会話や交流の雰囲気を大切にした空間と相性が良い活用方法です。
たとえば、事例で紹介した「OriHime」は身体に重い障がいがあって移動が難しい方でも、分身ロボットを指1本・視線入力などで操作でき、「その場にいる感覚」で接客できるのが特徴です。
人と人とのコミュニケーション体験自体に価値がある接客シーンでは、分身ロボットを活用するスタイルが適しているといえるでしょう。
とくに、障がい者雇用と社会貢献を来店動機にしやすい業態とマッチしやすいでしょう。
3-3. メタバース空間内で就労する形式:エンジニアや事務職など、集中作業型の業務に向いている
メタバース空間(仮想空間)上にオフィスを再現してアバターで出勤し、遠隔地から就労するスタイルは、エンジニアや事務職、クリエイティブ職など、個人の作業に集中することが求められる業務と相性が良いでしょう。
バーチャル空間上では、他のメンバーと自然に雑談したり、タイミングを見て相談したりと、「一緒に働いている感覚」を共有しながらチームで仕事を進めることができます。
現実の出社を前提としないため、障がいのある方はもちろん、通勤やオフィス環境への不安がある方にも無理のない就労スタイルを提供できます。
とくに、業務の多くがパソコン上で完結し、なおかつすでにリモートワークの体制がある程度整っている企業であれば、メタバースオフィスの導入は現実的な選択肢となるでしょう。
4. 障がい者雇用でアバターを活用する場合の導入ステップ

ここまで、アバター(分身のようなキャラクター)を活用した障がい者雇用の実例や導入のメリット、相性の良い業種についてなどを紹介してきました。
実際に「自社でも取り入れてみたい」と感じた方にとっては、「何から始めればいいのか」「どんな形式を選ぶべきか」といった疑問が生まれてくるかもしれません。
この章では、アバターを活用して障がいのある方に働いてもらうための具体的な導入ステップを、3つのフェーズに分けて解説します。
障がい者雇用でアバターを活用する場合の導入ステップ |
導入に必要な検討事項やサービス選定のポイント、スモールスタートの方法まで、実務的な観点から整理していますので、ぜひ参考にしてみてください。
4-1. どの形式が自社に向いているかを検討する
まずは、自社の業態や業務内容に応じて、どのアバター形式が適しているかを見極めることが第一歩です。
・接客業がメインなら、画面にアバターを表示するリモート接客型
・カフェや案内所など交流重視なら、分身ロボット型
・事務やIT系業務なら、メタバース型の仮想オフィス勤務型
といった形で、業務内容と接点がある形式を選ぶことが重要です。
4-2. 対応可能なシステムやサービスを比較・選定する
次に、実際のアバター接客や就労環境を支えるシステムやサービスを比較検討しましょう。
主な選択肢には以下のようなものがあります。
【障がい者雇用にアバターを活用する場合のサービス例】
アバター対応のリモート接客システム | ・AVACOM(AVITA株式会社) |
アバター分身ロボット | ・OriHime(株式会社オリィ研究所) |
メタバースオフィス | ・ovice(oVice株式会社) |
費用感は導入形式によって異なりますが、画面にアバターを表示させるリモート接客システムの場合、初期費用10万円程度、月額5万円程度から導入できるケースがあります。
一方で、分身ロボットやメタバースオフィスを導入する場合には月額制・機材費含めてやや高額になる傾向があります。
気になるサービスの資料請求をして、費用感も含めてしっかりと検討しましょう。
4-3. 小さく始めて段階的に広げるのがおすすめ
アバターを活用した就労を始める場合も、いきなりサービスを本格導入するのではなく、小規模な体制からスタートするのがおすすめです。
サービスによってはトライアル(テスト導入)が可能なので、まずはテスト的に導入して現場の使用感も含めて検討すると良いでしょう。
導入を進める場合も、いきなり全社・全店に入れるのではなく、まずは1店舗に設置してテスト稼働を行い、顧客の反応や運用上の課題を確認したうえで段階的に利用範囲を広げていくのがおすすめです。
AI接客アバター「WONDERGIRL powered by AVITA」のご紹介 | |
 「WONDERGIRL powered by AVITA」は、生成AIによる自動応対と有人オペレーターによる対応を切り替え可能な次世代型AIアバター接客サービスです。 AIだけでなく、必要に応じて人がリアルタイムで応対できる設計のため、在宅就労をベースにした障がい者雇用にも柔軟に活用できるのが大きな特長です。 開発はAIアバター実績が豊富なAVITA社による「AVACOM」サービスをベースとしており、安心の実績ある技術が活用されています。
多くのAI接客ツールは「AI前提」で設計されていますが、このツールはもともと有人対応からスタートし、後からAIを組み込んだ設計になっているため、他にはない柔軟性と接客品質の高さが強みです。 「複雑な問い合わせには人が対応」「基本的な案内はAIで効率化」といった場面に応じた切り替えができるため、対応可能なシーンが広く、顧客満足度を損なわずに省人化を実現できます。
導入実績豊富なAVITA株式会社が提供するアバター接客基盤「AVACOM」のパートナープログラムに参画し、その技術を活かしたサービスとして提供されているのがこの「WONDERGIRL powered by AVITA」です。 アバターによる遠隔就労を取り入れながら、顧客満足と省人化の両立を目指したい企業の方は、ぜひ一度ご相談ください。 サービス内容については、以下から資料をダウンロードできます。 |
5.まとめ
本記事では「障がい者雇用におけるアバター活用」について解説してきました。
最後に、要点を簡単にまとめておきます。
◆障がい者雇用でアバターを活用した事例
・コンビニの遠隔接客で障がい者を雇用している事例(ナチュラルローソン)
・テーブル上の分身ロボットを通して障がい者が接客を行う事例(OriHimeカフェ)
・メタバース空間に再現した仮想オフィスで障がい者が勤務する事例(Man to Man Animo株式会社)
◆障がい者雇用でアバターを活用するメリット
・法定雇用率の達成に向けた現実的な選択肢になる
・通勤点対面が難しい障がい者に無理なく働ける就労機会を提供できる
・新たな人材の活用で「現場の人手不足」を解決できる
◆障がい者雇用でのアバター活用が向いている業種・企業の例
・画面に表示されたアバターが接客する形式:コンビニや弁当店などと相性が良い
・アバターロボットを使って接客する形式:カフェや観光施設などの交流重視の場所に適している
・メタバース空間内で就労する形式:エンジニアや事務職など、集中作業型の業務に向いている
◆障がい者雇用でアバターを活用する場合の導入ステップ
・どの形式が自社に向いているかを検討する
・対応可能なシステムやサービスを比較・選定する
・小さく始めて段階的に広げるのがおすすめ
生成AIによる自動応対と有人オペレーターによる対応を両方行えるアバター接客サービスなら、ぜひ「WONDERGIRL powered by AVITA」をご検討ください。
#障害者雇用 #アバター


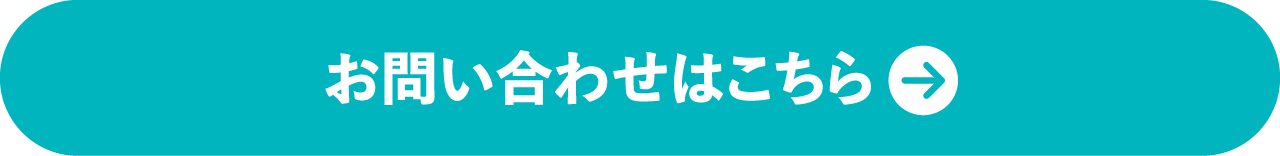
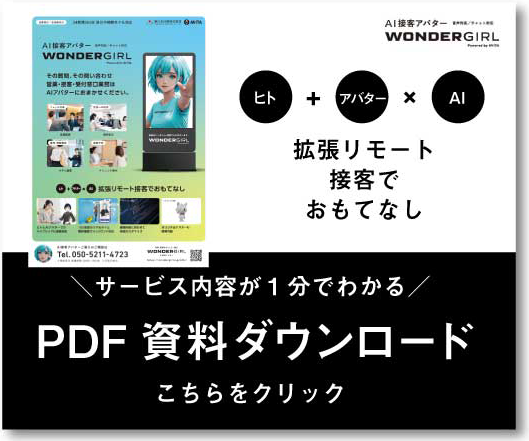
コメント