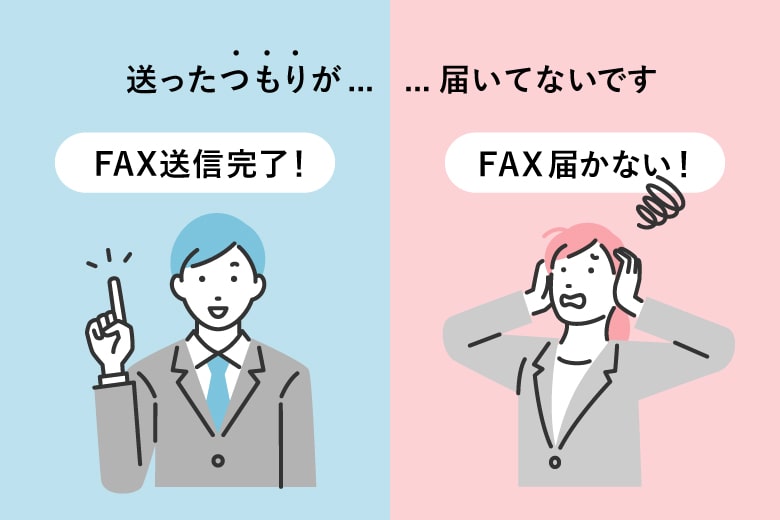
「FAX送ったかどうかも、もう分からないって言われるんですよ」
この一言に、受発注業務が抱える“見えない不安”の本質が表れています。
FAXは今なお多くの企業で使われていますが、「ちゃんと送ったか」「正しく届いたか」「間違えずに読めたか」といった一連の確認が曖昧になりやすく、ログや通知も残りません。
その結果、確認の電話が常態化し、二重送信や誤送信、担当者の属人化など、さまざまなトラブルが発生してしまいます。
この記事では、FAX送信をめぐる「送ったつもり」問題の背景と、それが業務に与える影響を深掘りし、BtoB取引における受発注業務を効率化するための“見える化”の仕組みづくりについても解説していきます。
【この記事でわかること】
|
目次
1.「FAX送ったはず」なのに届いていない原因

FAX送信は、「送ったつもり」になりがちな業務のひとつです。
その理由は、送信完了の確認が仕組み化されておらず、日々の業務の中で個々の担当者が「おそらく大丈夫だろう」と判断してしまっているためです。
また、紙でのやりとりという性質上、送った証拠や追跡が残らないことが多く、トラブルが起きても原因が特定しにくいという問題があります。
1-1. 問題1:確認が習慣化されていない
送信後に届いているか確認するルールが存在せず、「確認はしていないけど、たぶん届いているだろう」という感覚で運用されているケースが多くあります。
確認のプロセスが業務フローに組み込まれていないと担当者ごとの判断に委ねられてしまい、重要なFAXが届いていないことに後から気づくといった事態も少なくありません。
また、確認が曖昧なまま次の業務へと移行してしまうため、ミスが発覚するのは取引先からの問い合わせを受けた後というケースも多く、対応が後手になりがちです。
1-2. 問題2:ログが残らず、追跡も困難
FAX機器に送信履歴が残っていたとしても、社内でそれを都度チェックする仕組みが整っていないと、確認手段として機能しません。
たとえば、送信ボタンを押した後に「送信完了」の表示があっても、送信自体はできてしまうので、相手先に正しく届いたかどうかまでは分からないのが実情です。
加えて、送信履歴は機器側にしか残らないため、担当者が離席中・不在時に他のメンバーが情報を追えず、確認対応が滞ってしまうリスクもあります。
1-3. 問題3:読みにくさや紛失のリスク
送られたFAXが受信側では読みにくい状態で届いたり、プリントアウトされた紙が埋もれて気づかれないケースもあります。
特に、手書きの注文書や印刷がかすれている書類は、受け取る側にとって判読が困難です。
また、共有プリンターで受信したFAXが他の書類に紛れたり、必要な担当者に届かないまま放置されたりといった問題も起こります。
最悪の場合、注文そのものが処理されないまま時間が経過し、納期遅延やクレームに発展するリスクもあります。
1-4. 問題4:問い合わせ対応が日常化
これらの問題を放置していると、「念のため確認の電話をしておこう」「もう一度送っておこう」といった二重対応が日常化し、受発注業務のスムーズな進行を妨げる要因になってしまいます。
受注側では、日々の問い合わせ対応に追われることとなり、本来の業務が後回しになることも。
一方で発注側も、「届いていないかもしれない」という不安から毎回電話をかけるようになり、結果として両者の業務効率が下がってしまう悪循環に陥ります。
このように、FAXは「届いたかどうか」が非常に不透明な手段です。
送った側も受け取った側も確信を持てず、結果として「一応確認の電話をしておこう」という対応が日常化します。
電話での確認は数分で済むこともありますが、それが一日に何件も重なると、業務時間のかなりの割合を問い合わせ対応に取られるようになります。
2.FAXのトラブルが引き起こす受発注業務への影響
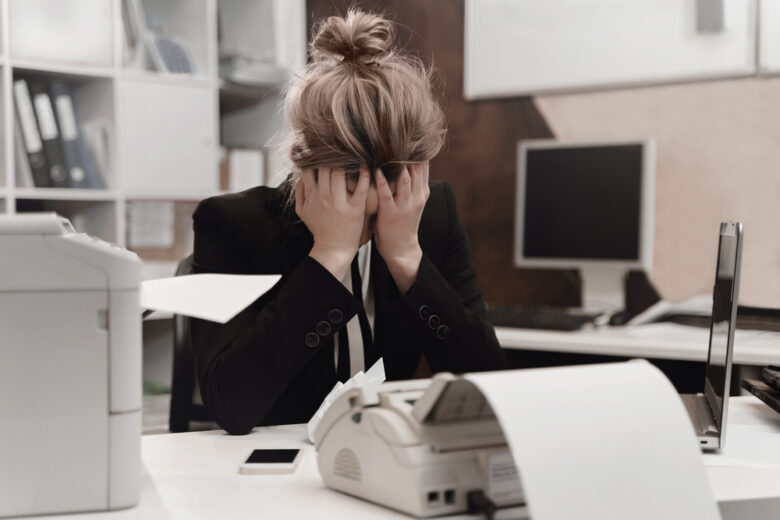
1章で見たような曖昧なFAXの運用は、実際の現場にどのような悪影響を及ぼしているのでしょうか。
ここでは、具体的な業務の流れにどんな影響が出ているのかを見ていきます。
2-1. 担当者の業務が中断される
FAX送信後に「届いていないのでは?」という不安から発注側が確認の電話をかけてくると、受注側の担当者はそのたびに対応に追われることになります。
業務の途中で電話がかかってくると、他の作業が中断され、集中力も途切れてしまいます。
これが1日に何件も重なると、受発注以外の業務全体に支障をきたす恐れがあります。
また、「どのFAXの話か」「何を送ったのか」といった情報を再確認する必要があるため、FAXの受信・確認・対応にかかる時間は想像以上に長くなります。
このような対応は、単なる確認であっても生産性を大きく下げてしまいます。
2-2. 属人化によって業務が滞る
FAXの確認を各担当者の記憶や経験に頼っていると、その担当者が不在の際に対応できる人がいないという問題が発生します。
「このFAXを送ったかどうか」「届いたかどうか」「どこまで確認しているか」といった情報が共有されていないと、問い合わせ対応やトラブル時の対応ができません。
また、対応の流れを誰もが見える形で管理できていないと、担当者ごとの確認方法や対応スピードに差が出てしまい、組織としての業務の安定性にも影響します。
2-3. トラブルの原因が特定できない
「送ったはず」「届いていない」の水掛け論になる原因のひとつは、記録が残っていないことです。
FAXには、メールのような送受信履歴や既読通知といったログが残らず、後から状況を振り返ることが非常に困難です。
そのため、発注側・受注側のどちらに非があるのかが分からないまま、関係性の悪化や不信感の増加につながるケースもあります。
結果として、再送や電話確認などの補足的な業務が常態化し、さらに手間が増えていきます。
2-4. 全体の進捗管理が難しくなる
受発注業務をFAXに頼っていると、「今どの注文がどこまで進んでいるのか」が分かりにくくなります。
各案件の進捗をFAXの送信や確認履歴から追うのは現実的ではなく、エクセルやメモ、個人のメールボックスなど、情報がバラバラに管理されることになります。
この状態では、進捗の把握・報告・確認が煩雑になり、部門間の連携や上司への報告にも支障が出てしまいます。
FAXを主軸としたアナログなやりとりが続く限り、情報共有や業務効率化は実現しづらいのが現実です。
3.FAXに頼らない受発注──「送ったつもり」から脱却するには

FAXトラブルを防ぐには、「FAXを使わない」という選択肢を現実的に検討する必要があります。
ただし、「完全にFAXを廃止する」のではなく、「FAXに依存しなくても大丈夫な仕組みを用意する」ことが重要です。
ここでは、FAXを前提としない受発注業務の仕組みと、それによって得られる効果について見ていきます。
3-1. 「ログが残る」仕組みづくり
FAXでは「送った証拠」が残りにくいのが最大の弱点です。
これに対して、オンラインの受発注システムであれば、注文の送信履歴が自動で記録され、日時や送信者、注文内容が履歴として蓄積されます。
一般的な受発注システムには、注文ステータス(未処理・出荷準備中・出荷済みなど)がリアルタイムで更新される仕組みがあり、バイヤー・サプライヤーの双方で共有することが可能です。
誰がいつ、どこまで処理したかといった情報が記録されることで、業務の属人化を防ぎ、万が一トラブルが発生しても原因の特定が容易になります。
こうした「ログが自動で残る環境」によって、曖昧だった受発注の証跡管理が明確になり、問い合わせやトラブルの発生件数を大幅に削減することができます。
3-2. 「進捗が見える」共有環境
FAXでは、注文の進捗や納期の変更、処理状況をリアルタイムで把握するのが困難でした。
これに対し、オンラインの受発注システムでは、関係者全員が同じ情報をリアルタイムで把握できる「共有のプラットフォーム」が実現します。
たとえば、商品を注文したバイヤーは、出荷ステータスの更新を都度確認できるため、「発注のFAXが届いていないかもしれない」という不安を感じることがなくなります。
サプライヤー側も、注文内容に不備があった場合や納期調整が必要な場合に、即座に修正・通知を行えるため、確認の電話や再送依頼が激減します。
また、進捗が見える化されるため、担当者が不在でも画面上で処理状況を確認できる点も、業務の安定性向上に寄与します。
このように、「ログが残る」「進捗が見える」環境を整えることが、「送ったつもり」からの脱却につながるのです。
4.FAXはゼロにできない?──段階的に進めるデジタル移行

「うちは取引先がFAXしか使えないから…」 そんな声も少なくありません。
多くの企業では、長年の取引関係や取引先のITリテラシーの問題から、「FAX文化」が根強く残っています。
そのため、「今すぐFAXをやめる」のは現実的でない場合もあるでしょう。
だからといってFAXに完全に依存したままでは、業務効率の改善も、トラブルの削減も期待できません。
重要なのは、“FAXを残しながらも、FAXに依存しない”仕組みを整えることです。
4-1. 手入力からの脱却:FAX OCRでFAX注文を自動データ化
FAXで届いた注文書をOCR(光学文字認識)で読み取り、自動的に受注システムへ取り込む仕組みを導入することで、紙で届いた情報を手作業で入力する手間を大幅に削減できます。
これにより、以下のような効果が期待できます。
- 注文情報の転記作業が不要になり、業務負担を軽減
- 手入力によるミスの防止
- 入力の自動化により、受注から出荷までのタイムロスを最小限に
OCRの精度も年々向上しており、定型フォーマットを活用すれば高い認識率を維持できます。
注文書のフォーマットをあらかじめ共有しておくことで、スムーズな運用が可能になります。
4-2. 情報の見える化:データ化された注文を一元管理
FAX OCRでデータ化された注文情報は、CSV形式で出力することができ、エクセルや基幹システムと連携した管理・分析が可能になります。
これにより、以下のような業務改善が実現します。
- どの取引先からどの商品がいつ注文されたかが一目瞭然
- リアルタイムでの進捗確認が可能
- 納期管理・在庫管理との連動によって、対応スピードが向上
たとえば、「今週はFAX注文が集中しそうな取引先がいる」といった予測も、データを活用することで事前に把握できます。
このように、「FAXを使いながら、FAXに依存しない」体制を整えることで、無理なく移行が進みます。
最終的には、FAX以外の注文手段(Webフォーム、メール、受発注システムなど)への移行を促しつつ、FAXを予備手段として残しておく形も可能です。
少しずつデジタルの比率を高めることで、現場の混乱を最小限に抑えつつ、業務改善を実現できます。
5.問い合わせ対応の手間を減らす対策3つ

受発注のやり取りで問い合わせが多い理由は、情報の流れが可視化されていないからです。
「送ったのに届いてない」「届いたかどうか分からない」「確認してもらえたか分からない」—— この“分からない” が積み重なることで、FAXトラブルが慢性化し、結果として問い合わせの連鎖を生んでいるのです。
こうした状況を改善するためには、次の3つの対策が効果的です。
5-1. 対策1:誰でも進捗が分かるようにする(ログ・ステータス・通知の整備)
受発注に関する情報がシステム上にログとして残ることで、「誰が、いつ、何を送ったのか」が可視化されます。
また、発注書が処理されたタイミングや納品予定などのステータスがリアルタイムに更新され、確認の手間が大きく軽減されます。
通知機能を活用すれば、処理状況の変化を関係者に自動で知らせることも可能になります。
5-2. 対策2:人に頼らず確認できる環境をつくる(画面での共有、システム化)
進捗状況を電話や口頭で確認するのではなく、システム画面で誰でも確認できるようにすることが重要です。
画面を共有することで、社内外の関係者が「自分で確認できる」状態になり、属人化や対応漏れのリスクが大幅に減ります。
5-3. 対策3:問い合わせが起きる前に伝える(自動通知や履歴共有)
「確認される前に伝える」という視点が、問い合わせを減らすカギとなります。
注文処理が完了したタイミングや、納品の直前に自動通知を送ることで、「いつ確認すればいいか分からない」といった不安を解消できます。
履歴もシステム上に残しておけば、担当者が不在でも過去のやりとりをすぐに追えるようになります。
これらの対策は、すべて「WONDERCART」のようなBtoB受発注システムを活用することで実現可能です。
「確認のための確認」が当たり前になっている現場にこそ、情報を「見える化」し、問い合わせの手間の連鎖を断ち切る仕組みが求められています。
6.WONDERCARTで実現するトラブルのない受発注
WONDERCARTは、FAXによって起こりうるトラブルを未然に防ぎ、業務負担を減らすためのBtoB受発注システムです。
代表的な機能
|
これらの機能を活用することで、以下のような課題を解消できます。
- 「ちゃんと送ったか分からない」 → 発注内容と送信履歴がシステム上に残り、誰がいつ何を送ったのかが可視化されます。
- 「正しく届いたか分からない」 → 発注処理状況がステータスでリアルタイムに反映され、進捗確認が不要に。担当者への自動通知も可能です。
- 「誰に聞けばいいか分からない」 → 社内外の関係者が同じ画面で情報共有できるため、担当者が不在でもスムーズに対応できます。
さらに、WONDERCARTでは、取引先ごとに表示商品や画面構成をカスタマイズすることも可能です。
これにより、掛け率の異なる取引先にそれぞれの画面を表示できます。
FAX文化が根強く残る業界においても、WONDERCARTは段階的なデジタル移行を支援し、日常的な問い合わせや二重対応を減らすことで、業務全体の生産性向上に寄与します。
「確認がいらない受発注」は、決して理想論ではありません。
WONDERCARTを活用することで、FAXによるトラブルのない受発注を実現できるのです。
7.まとめ
受発注におけるFAX運用の課題は、「送ったつもり」「届いたはず」といった担当者の判断に頼っている点にあります。
「FAXを送ったはず」なのに届いていない問題の原因はこちら。
- 確認が習慣化されていない
- ログが残らず、追跡も困難
- 読みにくさや紛失のリスク
- 問い合わせ対応が日常化
このような悪循環を断ち切るには、FAXを単に「やめる」ではなく、「見える化」を軸にした業務設計へと変えることが不可欠です。
本記事で紹介したポイントを改めて整理すると、次のようになります。
- 「FAXに頼らない仕組み」を整える
ログとステータス、共有画面による進捗の可視化が、“確認の手間”を減らします。
- 段階的に、FAXから脱却する
FAX OCRの活用でアナログ注文も自動処理。徐々にデジタル比率を高めることで、現場の負担なく移行が可能です。
- WONDERCARTで「確認のいらない受発注」を実現する
FAX注文も受け入れつつ、ログ・ステータス・通知・共有といった機能により、トラブルのない受発注体制をつくれます。
FAX文化が残る企業にとって、「今すぐ完全にやめる」のは現実的でないかもしれません。
けれど、やめる準備を始めることは、今すぐにでも可能です。
日々の「確認の電話」や「念のための再送」に悩んでいるのであれば、業務フローを見直すサインかもしれません。
\ 無料デモでFAXトラブルのない受発注を体感 /
WONDERCARTでは、実際の操作画面をご覧いただける無料のデモ体験をご用意しています。
FAX運用における問題をどう解消できるのか、ぜひ一度お試しください。

#fax #受発注 #トラブル


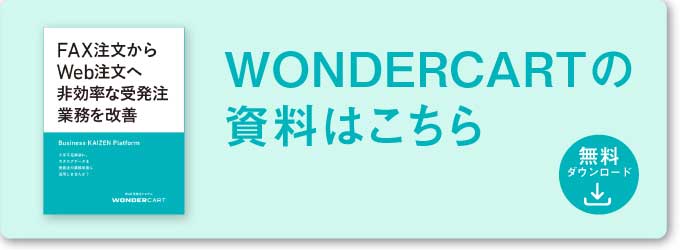
コメント