
「お客様ごとに注文の形式が違う」
「FAXか電話のどちらで注文されたかわからない……」
そんなお悩みを感じたことはありませんか?
BtoBの受注業務では、日々の注文がFAX、電話、メール、チャット、独自フォーマットのExcelファイルなど、実にさまざまな手段で寄せられます。
注文内容も、品番だけが書かれていたり、数量や希望納期が曖昧だったり、確認しないと処理できないものが少なくありません。
こうした「注文形式のバラつき」は、確認作業の手間を増やすだけでなく、ミスや対応遅れといったトラブルを引き起こす要因にもなります。
本記事では、なぜ注文方法が顧客や担当者ごとに異なってしまうのか、その背景を整理した上で、受注業務全体に与える影響と、トラブルを防ぐための現実的な改善方法をご紹介します。
【この記事でわかること】
|
目次
1. FAX、電話、メール——なぜ注文方法が統一されない?
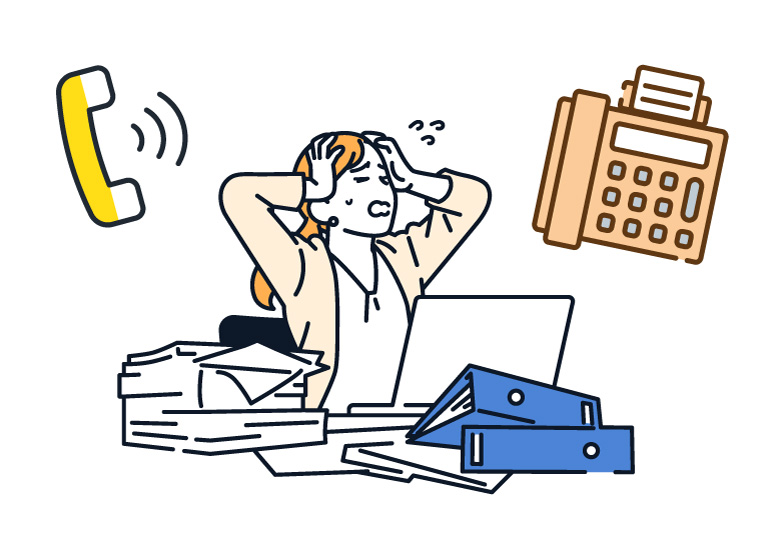
注文方法が顧客や案件ごとにバラバラで管理が大変——
この問題は、受注業務に携わる方であれば誰しもが一度は経験しているのではないでしょうか。
たとえば、ある顧客はFAXで商品番号と数量だけを送ってくる一方、別の顧客はメールの本文に注文内容を箇条書きで記載してくる。
中には、過去に送ったExcelファイルを使い回しているものの、書式が微妙に異なっていて確認に時間がかかる…といったことも。
さらに最近では、LINEやチャットで「前と同じものを」といった曖昧な注文が来ることも増えています。
なぜこのような状態が常態化しているのでしょうか?
そこには大きく分けて、次の3つの理由が存在します。
1-1. 理由①:顧客ごとに慣れたやり方が定着している
BtoB取引における受発注やり取りは、長年の信頼関係や業界特有の商習慣に基づいていることが多く、注文の形式が「なんとなく決まっている」ケースも少なくありません。
「今までもこれでやってきたから」という顧客側の慣れが、形式の見直しを難しくしているのです。
また、発注担当者が変わると、新しい担当者が自分のやり方で注文を出し始めることもあり、結果的に社内でも統一されていない注文形式がさらに複雑化することもあります。
1-2. 理由②:受け手側が柔軟に対応しすぎてしまう
受注側としては、顧客との関係を大切にするあまり、「どんな形でも注文してくれれば対応します」という姿勢を取ってしまいがちです。
もちろんこれは信頼関係の維持という意味で重要なことですが、一方で業務の効率性やミス防止という観点から見ると、大きなリスクにもなりえます。
「どんな形式でも対応する」という柔軟さは、裏を返せば「社内でその都度、人が内容を読み取って処理している」という属人的な仕組みで支えられているということです。
長期的には、担当者の負担増や処理品質のバラつきにつながります。
1-3. 標準化の手段や仕組みが整っていない
注文業務の標準化に取り組もうとしても、その手段や仕組みが整っていなければ、掛け声だけで終わってしまいます。
たとえば、受注フォーマットを作って配布しても、「使いづらい」「入力の手間がかかる」といった理由で定着しない。
あるいは、メール以外の発注チャネルを強制的に制限しようとしても、「かえって発注のハードルが上がってしまった」と顧客から反発されることにもなりかねません。
つまり、形式を統一するには、それに対応できる受け皿となる仕組みと、顧客側にも納得してもらえる運用ルールの両方が必要なのです。
注文方法がバラついているのは、決して誰かの怠慢や工夫不足ではありません。
それは、現場の努力不足ではなく、仕組みの整備がまだ十分でないことに根本的な原因があるのです。
次章では、このような状態がどのようにしてトラブルや業務の非効率を生み出してしまうのか、実際に現場で起こりがちなパターンをもとに掘り下げていきます。
2. 受注トラブルは、こうして起きる

注文の形式が顧客や案件ごとに統一されていない状態は、単なる業務上の煩雑さにとどまらず、深刻なトラブルの引き金にもなりかねません。
それは、受注トラブルを引き起こす温床になっているのです。
「商品が違う」
「数量が間違っていた」
「納期に間に合わなかった」
——どれも、現場では珍しくないクレームの一部です。
けれど、ひとつひとつを追ってみると、根本には必ず「確認作業の曖昧さ」や「情報の不一致」が潜んでいることがわかります。
ここでは、BtoB現場で実際によく起きているトラブルを例に、その背景にある構造的な課題を探ってみます。
2-1. ケース①:書式が違っていて見落とした
ある顧客からの注文書は、普段と異なるフォーマットで届きました。
いつもは「商品名+品番+数量」が一覧になっていたのに、今回は商品名が省略され、品番と数量だけが記載されていたのです。
受注担当者は時間に追われていたため、内容をざっと確認しただけで処理を進めてしまいました。
ところが、納品後に顧客から「違う型番のものが届いている」と連絡が。よく確認してみると、品番が1桁違っていたことに気づきました。
原因は注文書の形式が変わったことによって、「いつもと違う構成」に気づかず、確認を省略してしまったこと。
本来ならチェックすべき項目が書式によって見えづらくなっていたのです。
2-2. ケース②:チャット注文で情報が抜けていた
別の顧客は、いつもチャットで簡単に注文をしてくるタイプです。
「この前と同じやつ、20個お願い」とだけ書かれたメッセージを見て、担当者は「たぶんこれだろう」と過去の履歴を探して発注処理を進めました。
ところが、実は前回の注文時とはロット番号が変わっており、数量も最終確定前だったことが後で判明。
納品後にクレームとなり、返品・再配送の対応に追われることに。
口頭やチャットによる「曖昧な依頼」は、表現のずれや認識のギャップを生みやすく、確認が不十分なまま進めることで大きなトラブルを招いてしまうのです。
2-3. ケース③:属人化により、担当不在で対応できなかった
発注が来るたびに、特定の担当者が過去の取引履歴や価格表、納期情報を手元のファイルで確認して対応していたケース。
その担当者が急遽休んだ日に限って、急ぎの発注依頼が入りました。
しかし、情報の保管場所や判断基準がその人にしか分からず、周囲は混乱。
「戻ってきてから確認します」と返答せざるを得ず、納期が遅れてしまいました。
「この人しかわからない」状態は、業務の属人化が引き起こす典型的なリスクです。
その場しのぎでなんとか回っていたとしても、いずれ大きなトラブルに発展しかねません。
注文書式の違い、曖昧な依頼、属人化——これらはすべて、情報が整理されずに散らばったまま運用されていることの表れです。
つまり、トラブルの本質は「発注内容のバラつき」ではなく、それを支える仕組みや運用が標準化されていないことにあります。
次章では、こうした課題から抜け出す第一歩として、注文を「標準化」するメリットと、その進め方について具体的にご紹介していきます。
3. 注文業務の「標準化」がもたらすメリット

トラブルの原因が情報の分散や形式のバラつきにあるなら、その解決策の一つが注文業務の「標準化」です。
「標準化」と聞くと、少し堅苦しく感じるかもしれません。
けれどその本質は、誰がやっても迷わず処理できる状態をつくること。
これは、受注担当者の負担軽減はもちろん、組織全体の生産性と信頼性を高めるためにも非常に重要な取り組みです。
この章では、注文業務を標準化することで得られる主なメリットを、現場の変化として実感しやすい形でご紹介します。
3-1. メリット①:処理スピードの大幅な向上
注文内容が統一された書式で届くようになれば、何を・いくつ・いつまでに、という情報を毎回確認し直す必要がなくなります。
商品マスタとの照合、在庫や納期の確認、伝票の作成なども、あらかじめ決まった流れの中でスムーズに処理できるようになります。
その結果、「1件あたりにかかる処理時間」が大幅に短縮。
繁忙期や急ぎの案件にも柔軟に対応できる余裕が生まれ、本来注力すべき提案業務や改善活動に、時間を割けるようになるのです。
3-2. メリット②:確認・修正のやりとりが減る
注文形式がバラついていると、どうしても「数量の記載漏れ」「品番の誤記入」「納期の曖昧さ」といった、確認すべき点が多くなりがちです。
一方で、注文フォームやシステムを使って必要事項が事前に明確になっていれば、確認作業は最小限で済みます。
結果として、顧客とのやりとりの回数が減り、対応のスピードと精度が両立できるようになります。
また、「前回の注文内容をコピーして出してくれればいい」といった曖昧な依頼も減り、思い込みによる誤処理を未然に防ぐ効果もあります。
3-3. メリット③:属人化から脱却できる
標準化された注文フローを整えることで、「この顧客は誰々さんじゃないと対応できない」といった属人化を防ぐことができます。
たとえば、受注管理システムや共有フォーマットの導入により、顧客ごとの価格条件や過去の取引履歴を誰でも確認できるようにすれば、担当者が休んでも業務が滞ることなく回せる状態になります。
これは単なる業務効率の問題にとどまらず、人材の引き継ぎや教育にも好影響を与え、組織としてのレジリエンス(回復力)を高める取り組みにもつながります。
リアルタイムで在庫情報が「見える」ようになれば、営業のスピードも、顧客対応の質も、社内連携の円滑さも、大きく向上します。
とはいえ、リアルタイム在庫の「見える化」には、仕組みとツールの工夫が欠かせません。
次章では、それを可能にする受発注システムの活用方法と、導入によって得られる具体的なメリットをご紹介します。
4. 受注業務を支えるツールの力

「注文業務を標準化したい」と思っても、現場ではこうした声が上がるかもしれません。
「仕組みを整えるって、つまりシステム導入ってことでしょ?」
「でもウチのやり方に合うかどうか分からないし、費用も手間もかかるんじゃないの?」
確かに、何かを新しく始めるには不安がつきものです。
特にBtoBの受発注業務は顧客ごとの事情も多く、ひとつのやり方に合わせること自体が難しいと感じている方も少なくないでしょう。
ですが今では、現場の運用を尊重しつつ、「属人化」や「確認の煩雑さ」を解消できる受発注ツールが多数登場しています。
この章では、受注業務を支える代表的な機能や、導入によって得られる具体的な効果について見ていきましょう。
4-1. 注文内容を「構造化」して受け取る
受発注ツールを活用する最大のメリットのひとつは、「構造化された注文情報」を受け取れることです。
たとえば、顧客がログインして専用の注文画面で商品を選ぶ形式であれば——
- 品番・商品名・数量・希望納期
- 過去の注文履歴
- 発注者情報・部署・備考欄
といった、必要な情報がもれなく入力された状態で注文が届くようになります。
これにより、毎回の「確認のやり取り」や「記載漏れチェック」の工数が、劇的に減らせます。
4-2. 商品情報と連携し、ミスなく処理できる
注文データと商品マスタ(品番・仕様・単価など)を連携させることで、入力ミスや誤処理のリスクも大幅に軽減できます。
たとえば、商品名を手入力していた頃は表記ゆれや入力漏れが原因で誤出荷が起きていたケースでも、マスタ選択式にすることで一貫性が保たれ、チェック工数も最小限になります。
さらに、価格条件や得意先ごとのルールがあらかじめ設定されていれば、「あれ、この商品はこの金額でよかったっけ?」と迷うこともなくなります。
4-3. ステータス・履歴管理で、引き継ぎも安心
受発注ツールでは、注文受付から納品・請求までのステータスを段階的に可視化することができます。
- 「注文受付済」
- 「社内確認中」
- 「出荷準備完了」
- 「納品済」
といった進捗が管理画面上で共有できれば、誰がどこまで対応したかをチーム内で即座に把握できるようになります。
担当者が休んでも、周囲が状況を引き継ぎやすくなり、トラブル回避にもつながります。
4-4. ツール導入は業務の土台を整えること
受発注ツールは、単に作業をラクにするだけの仕組みではありません。
むしろ、「仕組みでミスや属人化を防ぐ」ための業務基盤そのものです。
ツール導入というと、「大がかりな改革」や「ITへの置き換え」と捉えられがちですが、実際はもっと柔軟で、現場のやり方に合わせてカスタマイズできるものも多く存在します。
重要なのは、現場に合った形で仕組みを整え、誰でもミスなく対応できる流れを築くこと。
そうすれば、属人化を脱し、トラブルに追われる毎日から少しずつ抜け出すことができます。
受発注業務にツールを取り入れるということは、属人的な運用から、仕組みで支える業務への転換を意味します。
次章では、こうした仕組みが「取引先にも使いやすい形」であることが、スムーズな定着のカギになるという点についてご紹介します。
5. システムが定着するかどうかは「取引先の使いやすさ」がカギ

せっかく受発注システムを導入しても
「思ったほど使われていない」
「結局、電話やFAXでの注文が続いている」
そんな声を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
このようにシステムが思うように活用されない背景には、「システムが自社の都合で作られている」というギャップが潜んでいます。
自分たちの使いやすさだけではなく、相手(取引先)にも、日常的にストレスなく使ってもらえるかが重要です。
ここを見落とすと、どんなに高機能なシステムでも、結局は使われずに終わってしまいます。
5-1. 導入しても、相手が使わなければ意味がない
受発注システムの多くは、受注側(発注される側)にとっての利便性を中心に設計されています。
- 社内の伝票処理がラクになる
- 確認作業や入力ミスが減る
- 業務フローが自動化される
こうしたメリットは確かに大きいのですが、それだけではシステムは定着しません。
重要なのは、「発注する側」にも使いやすさや利点を実感してもらえるかどうか。
使いにくい、面倒、時間がかかる——そんな印象を持たれた時点で、発注者はこれまで通りの手段(電話・メール・FAX)に戻ってしまいます。
5-2. 取引先が使いたくなるシステムの条件とは?
では、取引先にも継続的に使ってもらえるシステムとは、どのようなものなのでしょうか?
ポイントは以下のような観点です。
- 簡単にアクセスできる
→ パスワード管理に手間取る、複雑な認証があると、初回以降使われなくなります。 - スマートフォンでも操作しやすいUI
→ 外出先や店舗からの発注が多い業種では、モバイル対応が必須です。 - 過去の注文履歴から再発注できる
→ いつもの注文を数クリックで完了できると、定着率が飛躍的に上がります。 - 注文内容の確認・修正が簡単にできる
→ ミスがあっても気軽に修正できる設計は、心理的ハードルを下げます。 - 導入時にマニュアルなしでも直感的に操作できる
→ 教える手間がない=導入負荷が小さいという評価につながります。
こうした細やかな配慮が、「発注する人の立場に立ったシステム設計」につながります。
5-3. 取引先に使ってもらう前提でシステムを選ぶ
受発注業務は、相手あってこそ成り立つプロセスです。 だからこそ、自社の業務効率だけを目的とするのではなく、「使ってもらいやすい仕組みかどうか」という視点が極めて重要になります。
いくら自社が便利になっても、発注者が使いにくいと感じてしまえば、結局は非効率なやりとりに逆戻りしてしまいます。
この事実は、受注業務のDXを検討する上で、常に意識しておくべきポイントです。
取引先が「使ってみよう」と思えるシステムとは、お互いの業務をスムーズにするという共通の目的を感じられるツールです。
だからこそ、受発注システムの導入は、単なる業務改革ではなく、取引先との信頼関係を一歩深める機会でもあります。
次章では、注文業務のトラブルを減らし、現場を効率化するためにオススメな受発注システムをご紹介します。
6. 現場の変化を支える「WONDERCART」という選択肢
「業務を効率化したい」「属人化をなくしたい」と感じていても、「どんなシステムを選べばいいのかわからない」「取引先が使ってくれるか不安」という声は少なくありません。
そこでご紹介したいのが、BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」です。
WONDERCARTは、50年以上にわたり業務用カタログを手がけてきた新日本印刷が開発した、受発注業務をまるごと一元管理できるクラウドサービス。
BtoB受発注の現場を熟知しているからこその発注側・受注側のどちらにも配慮された設計で、受発注業務全体のスムーズな運用を支えます。
| WONDERCARTの主な機能と効果 |
受発注業務にWONDERCARTを取り入れることは、「人に頼らず、仕組みで支える」業務へのシフトにつながります。 |
7.まとめ:確認の負担をなくすには仕組みの見直しから始めよう
本記事では、BtoBの受発注業務における在庫確認や注文処理の裏側に、どのような課題や負担が潜んでいるのかを整理しながら、その課題を人の頑張りではなく、仕組みで解決する方法をご紹介してきました。
「在庫の確認に時間がかかる」「注文情報が散らばっている」──こうした日々の負担は、多くの現場で当たり前になりがちです。
けれど、情報の見える化や共有の仕組みを整えることで、業務は確実に変わっていきます。
【この記事のポイント】
|
その第一歩は、業務の「やり方」ではなく、「仕組み」に目を向けることです。
業務改善のヒントは、すでに目の前にあるかもしれません。
「現場に合う仕組みって、どんなものだろう?」──そう思った方は、まずはデモで使いやすさを体感してみてください。
\無料のデモ体験実施中!/


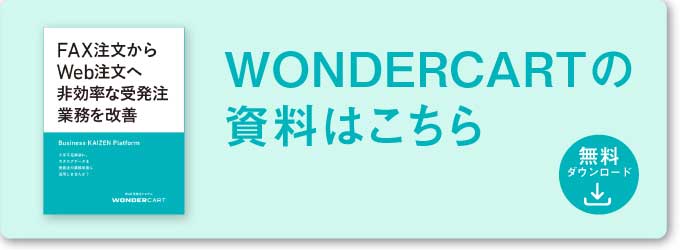

コメント