
「うちの取引先は年配の方が多くて、パソコンとか苦手なんですよ」
受発注業務をデジタル化しようとすると、こうした声が必ずと言っていいほど出てきます。
効率化のためにシステムを導入しても、相手がそれを使いこなせなければ意味がない──その気持ちはよくわかります。
無理をして押しつけるような形になってしまっては、逆に信頼関係にヒビが入ることさえあるかもしれません。
ですが、だからといってFAXや電話といったアナログ手段に依存し続けていては、人的ミスや確認漏れ、対応の属人化など、業務改善が進まないのもまた事実です。
この記事では、BtoB現場における「ITが苦手な取引先」に寄り添いながら、どうすれば負担なく受発注業務のデジタル化を進められるのかをやさしく解説します。
目次
1. 「パソコンが苦手だから無理」──あきらめが生む停滞

「システムを使えばもっと楽になるのに…」そう思っていても、相手に伝えるのは簡単ではありません。
たとえば、こんな声はありませんか?
「取引先の担当者は年配の方で、ITツールは使いこなせない」
「前にも説明したけど、結局また電話がかかってくる」
「そもそもパソコンを開く習慣がない」
このような声は、システムの導入を検討する際の第一の壁とも言えるでしょう。
1-1. なぜ、導入前にあきらめてしまうのか?
こうしたあきらめの多くは、「難しそう」「面倒そう」といった漠然とした感覚に起因しています。
実際に操作してみたわけでもなく、きちんと説明したわけでもないのに、最初から「どうせ無理」と決めつけてしまっているケースも少なくありません。
とくにBtoBの関係性においては、「お客様に強くは言えない」「余計な手間をかけさせたくない」という心理も働きやすく、デジタル化の提案そのものが先送りにされる傾向があります。
1-2. 「紙でいいでしょ?」に言い返せない背景
「紙のほうが見やすいし、慣れてるから」と言われたら、たしかに否定はしにくいものです。
しかしその言葉の裏には、「新しいものに触れる不安」や「覚える手間をかけたくない」という本音が隠れていることも多いのです。
そのような抵抗感に対して、無理に説得しようとしてもうまくはいきません。
必要なのは、「これなら私にもできるかも」と思える仕組みを用意することです。
つまり、苦手意識があることを前提とした入りやすい設計が、導入の成否を左右するのです。
そのためにはまず、「システムを使わずにアナログのまま対応を続けると、現場ではどんな負担やリスクが発生しているのか」を具体的に理解することが大切です。
次章では、一見すると単純に見える日々のやり取りが、なぜ業務全体の停滞を招いてしまうのか。その実態を詳しく見ていきます。
2. ITリテラシーが低い現場で起きている非効率
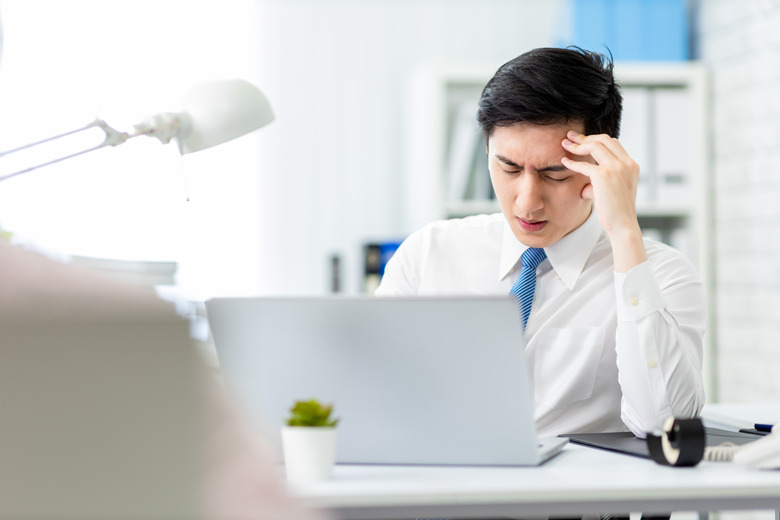
「これ、どう入力すればいいの?」
「今まで通り、FAXの方が安心だし…」
「IDとパスワードって、どこに書いてあるんだっけ?」
こうしたやりとりは、決して珍しいものではありません。
ITリテラシーが高くない現場では、ちょっとしたわからないが、業務の停滞や混乱につながることも少なくないのです。
2-1. 「使いこなせない」のではなく「触れたことがない」
「デジタルが苦手」とひとことで言っても、その背景は人によってさまざまです。
たとえば、そもそも普段の業務でパソコンやタブレットに触れる機会が少ない人にとっては、
「ログインして使う」
「情報を入力する」
「確認して送信する」
といった動作自体が、すべて新しいチャレンジになります。
こうした現場では、「システムを使えば早い」「オンラインで済ませればラク」といった発想がそもそも出てこないこともあります。
システムは使える人だけのものという空気が生まれてしまい、業務の中に浸透していかないのです。
2-2. その「ひと手間」が、全体の非効率に
ITリテラシーの違いが引き起こす問題は、本人だけにとどまりません。
たとえば、次のような場面はありませんか?
- パスワードの再発行やログインエラーの対応で、管理担当がたびたび呼ばれる
- 操作説明のために、都度電話や訪問でサポートが必要
- 結局紙や電話に戻ってしまい、デジタル情報とアナログ情報が混在
- 「わからないから確認しておいて」と頼まれた内容を別の担当がフォロー
このように、「使いづらい」「わからない」と感じている人が一定数いると、その分だけ全体の業務スピードが落ちることになります。
また、情報の入力や更新が滞れば、せっかくのシステムも最新の情報が反映されない使えない仕組みになってしまいます。
2-3. 定着は「人」に合わせた仕組みがあってこそ
業務のデジタル化を進めるうえで重要なのは、使う人のレベルに合わせて、段階的にステップアップできる設計をすることです。
「誰でも迷わず使えること」
「少しずつ慣れていけること」
「わからないときにすぐ頼れる仕組みがあること」
これらの要素が揃っていないと、どれだけ便利なシステムでも、使う人の不安や苦手意識が先立ち、現場に根づくことはありません。
また、ITリテラシーに差がある現場こそ、「自動化」や「一元化」で人の手間を減らす工夫が大切です。
入力補助や検索機能、帳票の自動作成など、使う人が「覚える手間」よりも「便利さ」を実感できるような仕組みでなければ、せっかくのシステムも活かしきれません。
「一見簡単そうに見える作業ほど、実は現場では手間がかかっていることもあります」
このギャップを埋めるためには、「ITが苦手な人に合わせる」発想が必要です。
次章では、そうした視点で設計された「簡単に使える受発注システム」が、どう現場を支えるのかを掘り下げていきます。
3. 必要なのは「誰でも使える」システム設計

「こんな簡単なこともできないの?」 「なんでマニュアルを読まないんだろう」 ──そんな言葉が、現場から聞こえてくることはありませんか?
ですが、デジタルツールの得手不得手は、人によって本当にさまざまです。
重要なのは、使う人のスキルを上げるよりも、誰でも迷わず使える設計にすること。
つまり、人にスキルアップを求めるのではなく、誰にとってもわかりやすい仕組みにこそ改善の余地があります。
3-1. 「使えない」のではなく「設計が合っていない」
「せっかくシステムを導入したのに、誰も使ってくれない」 「システム操作に苦手意識がある社員が足を引っ張っている」 といった声を聞くこともありますが、問題は「人」ではなく「設計」にあります。
たとえば、
- 操作手順が多すぎて途中で挫折する
- 表示項目が専門用語だらけで意味がわからない
- 一度操作ミスをすると戻せない
- 必要な情報がどこにあるのかわからない
こうした状態では、どれだけサポートしても、「またわからなくなりそう」「ミスが怖い」という不安が先に立ち、使う人の意欲そのものが削がれてしまいます。
一方で、「このボタンを押せば完了」「間違えてもすぐやり直せる」といった安心感のある仕組みなら、ITに不慣れな人でも前向きに取り組めるようになります。
3-2. 「誰でも迷わず使える」システムとは?
「誰でも使える」とは、単にマニュアルを用意するということではありません。
以下のような要素が揃ってはじめて、「本当に使いやすい」と実感できるシステムになります。
- 操作がシンプルで直感的:ボタンの位置や文言がわかりやすく、迷わず進める
- よく使う機能がすぐに見つかる:探す時間が減り、操作ストレスも軽減
- 入力補助がある:品番や単価が自動入力されるなど、人的ミスを防げる
- スマホ・タブレットにも対応:現場でも、移動中でも利用しやすい
- 万が一のときに戻せる・確認できる:安心して触れる仕組みがある
つまり、「わからないから触りたくない」ではなく、「触ればすぐにわかる」システムをつくることが、現場への定着を促します。
3-3. システムに不慣れな人が使い続けたくなる設計
「誰でも使える」を一歩進めると、「誰でも使い続けたくなる」が見えてきます。
継続して使われるシステムには、以下のような特徴があります。
- 成功体験が得られる(初めてでも正しく操作できた)
- 操作のたびに負担が減る(作業が早く終わる実感がある)
- トラブル時にすぐ対応できる(問い合わせ先が明確)
こうした積み重ねが、「使ってもらう」から「使いたくなる」への変化を促します。
ITリテラシーの高い人だけが得をするのではなく、誰もが等しく業務効率の恩恵を受けられる仕組みこそが、真に現場に根づくデジタルツールだと言えるのです。
現場の誰もが「使えた」「できた」と思える体験を重ねることで、少しずつ、システムは抵抗する対象ではなく、味方となる存在へと変わっていきます。
次章では、こうした「誰でも使える仕組み」を実現する受発注システムについて解説します。
4. 「パソコンが苦手」でも定着する簡単な受発注システム

「パソコンが苦手な人でも使える」──これは受発注システムを選ぶうえで、非常に重要な視点です。
いくら多機能でも、使う側がストレスを感じてしまえば、業務の効率化どころか、混乱のもとになってしまうこともあります。
特にBtoBの受発注業務においては、取引先の担当者のITスキルにばらつきがあることも珍しくありません。
そうした現場でも定着しやすいのが、「迷わず」「短時間で」「誰にでも使える」といった設計がされた受発注システムです。
4-1. ポイントは「直感的操作」と「手間の少なさ」
実際にシステム導入を検討する際、「使いやすさ」を測る目安は以下のような点に表れます。
- ログイン〜注文までのステップが少ない
→ 複雑な手順がなく、マニュアルを見ずに進められる
- 見たい情報が一画面に整理されている
→ 品番、金額、在庫、納期など、探し回る必要がない
- スマホやタブレットでも同様に操作できる
→ オフィス外でも確認・操作が可能
- 「あの商品」と言われても過去履歴ですぐ特定できる
→ 電話やメールでの確認作業を省略できる
こうした「つまずかない仕組み」が整っていることで、パソコンに不慣れな人でも安心して利用できます。
「よくわからないから触らない」ではなく、「触ってみたら意外とできた」という体験が、システムへの心理的なハードルを大きく下げてくれるのです。
4-2. 現場視点での設計が定着のカギ
簡単なシステムとは、機能が少ないということではありません。
あくまで「使い手の立場で、無理なく使えるように設計されているかどうか」がポイントです。
たとえば、次のような工夫があると、現場の定着率は格段に上がります。
- 最初に開くページが「いつもの注文ページ」になっている
- 入力欄に例文が書いてある、または候補が表示される
- エラーが出た時の説明がやさしく、再入力しやすい
- 「この操作をするとどうなるか」が事前にわかるUI
こうした配慮は、パソコンに慣れていない人だけでなく、すべての担当者にとっての負担軽減につながります。
また、教える側にとっても「教えやすい設計」であれば、引き継ぎやサポートの手間も最小限に抑えられます。
4-3. 「簡単なシステム」で変わる現場の雰囲気
簡単に使えるシステムは、単なる業務効率化にとどまらず、現場の雰囲気そのものを変える力を持っています。
- 新しいことに前向きになれる空気が生まれる
- 自信のなかった人も「自分にもできた」と思える
- やり取りのミスが減り、信頼関係が深まる
結果として、「属人化の解消」や「取引先とのスムーズな連携」といった本質的な改善につながっていきます。
| 誰でも使える簡単な受発注システム 「WONDERCART(ワンダーカート)」 |
「WONDERCART(ワンダーカート)」 は、パソコンが苦手な方にもわかりやすい設計と、BtoB取引に特化した機能で、はじめてでも迷わず操作できる受発注システムです。
ITに不慣れな方でも「できた」と実感できる、やさしい仕組みで、社内外の業務負担をぐっと軽減します。 \無料デモ体験実施中/ \資料ダウンロードはこちら/ |
5.「システムが苦手」な取引先に導入するための4ステップ

受発注システムの導入でよくある悩みが、「取引先にどう伝えるか」「使ってもらえるか不安」といった導入時のハードルです。
特に相手が「パソコンが苦手」「新しい仕組みに消極的」といった場合、自社でどれだけ準備を整えても、実際に使ってもらえなければ意味がありません。
ですが、いきなり「システムを使ってください」とお願いするのではなく、段階を踏んで少しずつ慣れてもらうアプローチを取ることで、スムーズな導入が可能になります。
ここでは、実際の現場でも効果的な導入のための4ステップをご紹介します。
5-1. ステップ1:「試してもらう」ことから始める
「このシステム、使ってください」とお願いするよりも、 「一度、試してみませんか?」と声をかける方が、心理的ハードルはぐっと下がります。
そこで効果的なのが、デモ体験の提供です。
- たとえば、取引先の自社商品をあらかじめ登録した簡易デモ画面を用意しておき、実際に触ってもらう
- 「このボタンを押すと商品が見られます」「ここを選ぶと注文できます」と、たった数クリックで完了する流れを体験してもらう
- スマホやタブレットでも操作できる画面で、「これなら現場でも使えそう」と感じてもらう
このように、見せて説明するのではなく、触ってもらうことで、「なんだ、簡単なんですね」と思ってもらうことができます。
特にWONDERCARTのように、初めてでも直感的に操作できる設計のツールであれば、体験のハードルはさらに低くなります。
5-2. ステップ2:スモールスタートで運用に慣れてもらう
いきなり全ての取引をデジタル化しようとすると、相手の負担は大きくなってしまいます。
そこで有効なのが、「一部の業務から小さく始める」スモールスタートの考え方です。
たとえば、
- 最初は月に1〜2回しか発生しない定番商品の注文だけをシステムで処理してもらう
- 納品書だけはPDFで確認してもらい、注文は今まで通りFAXや電話で行う
- 注文書の記入だけシステムからできるようにして、印刷してFAXしてもらう形式にする(システムには履歴が残る)
このように、「相手の現場を急に変えすぎない」配慮が、結果的に定着の近道となります。
「まずはこの操作だけでOK」「不安なら紙と併用でも大丈夫」といった声かけが、信頼にもつながります。
5-3. ステップ3:導入後もこまめにフォローする
一度使ってもらっても、何かトラブルがあった際に頼れる人がいなければ、相手はすぐに元のやり方に戻ってしまいます。
そのためには、
- 初回利用後に「使いにくい点はなかったか」とヒアリングする
- 操作マニュアルは紙とPDF両方で用意し、迷ったときにすぐ確認できるようにする
- 電話・画面共有などでのサポート体制を事前に伝えておく
こうしたフォローが「安心感」となり、「また使おう」という気持ちにつながっていきます。
5-4. ステップ4:メリットを体感してもらう
相手が「使って良かった」「便利だった」と感じる瞬間をつくることが、継続利用の決め手です。
たとえば、
「注文履歴を確認できて助かる」
「いつもの商品がすぐ出てくるから楽」
「電話をかける回数が減った」
こうした体感が積み重なることで、「面倒そうだからやめる」ではなく、「これは便利だから続けたい」へと変わっていきます。
このように、「試す→小さく始める→丁寧に支える→価値を感じてもらう」という流れで進めることで、システムに対する不安は自然と解消され、取引先にとっても使いやすいツールとして受け入れられるようになります。
6. まとめ:誰でも使える「簡単さ」が、業務改善の第一歩
「パソコンが苦手だから」「取引先に負担をかけたくないから」──そんな理由で、受発注のデジタル化に踏み出せない企業は少なくありません。
ですが、システムが難しそうと感じられるのは、多くの場合、「使う人に合っていない仕組み」になっているからです。
本記事では、
- なぜITリテラシーの壁が導入の障壁になるのか
- 現場で起きている見えない非効率とは何か
- 誰にでも迷わず使えるシステム設計とはどんなものか
- システムが苦手な取引先にスムーズに導入する方法
について、丁寧に整理してきました。
ポイントは、「人を変えようとしないこと」。
苦手な人がいて当たり前、という前提で、誰でも触れる・迷わない・続けられる仕組みを用意することが、受発注業務の改善には欠かせません。
その第一歩として、「簡単に使える受発注システム」を体験してみるのはいかがでしょうか。
業務のやり方を根本から変えるのではなく、あくまで現場に寄り添った効率化から始める──それが、無理なく続く業務改善につながっていきます。
「WONDERCART(ワンダーカート)」では、誰にでも使いやすいUI設計と、導入から運用までの丁寧なサポートを通じて、取引先とのスムーズな受発注体制づくりを支援しています。
\無料デモ体験・資料ダウンロードはこちらから/



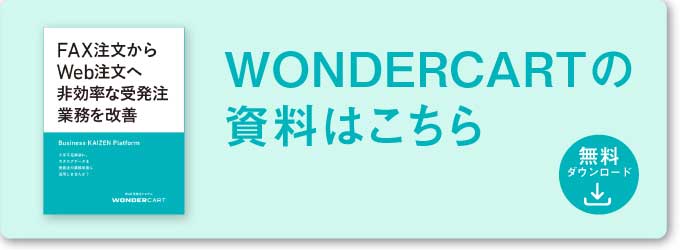

コメント