
「発注書、届いていませんか?」
「FAXが流れてなかったみたいです」
——そんなやり取り、まだ現場で続けていませんか?
BtoBの受発注業務は、今なおFAXや電話、メール、エクセルといったアナログな手段に頼っている企業が少なくありません。
それで業務が回っているように見えても
- 転記ミス
- 確認漏れ
- 発注忘れ
- 重複発注
- 属人化によるブラックボックス化
などの問題が慢性的に発生しており、「そろそろ限界を感じている」という声が多くの現場から聞こえてきます。
一方で、受発注システムを検討しようとすると、こんな疑問も出てきます。
「何を基準に選べばいいの?」
「うちの業務に合うシステムってどれ?」
「パッケージ型?カスタマイズ?フルスクラッチって何?」
選択肢が多く、それぞれの違いや導入のメリット・デメリットがわかりづらいため、検討が止まってしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、BtoBの受発注業務を効率化したい企業のために、
- よくある課題とシステム導入の必要性
- 開発スタイルごとの特徴と選び方
- 比較検討時に見るべきポイント
- 業界・業務特性に応じた選定のコツ
- そして、ちょうどいい選択肢としてのWONDERCARTの魅力
を、わかりやすく整理してご紹介します。
「どのシステムが有名か?」ではなく、「自社にとって何が最適か?」を考えるための判断軸が見つかる内容になっています。
それではさっそく、受発注業務の現場でよくある課題から見ていきましょう。
目次
1.BtoB受発注業務のよくある課題とデジタル化の必要性

BtoB取引における受発注業務は、企業の売上や信用にも関わる重要な業務です。
それにもかかわらず、FAXや電話、メールといったアナログな手段に頼ったままのケースが少なくありません。
一見すると「今まで通り」で大きな問題がないように見えても、実際には多くの現場で、ミスや手間、属人化による非効率といった課題を抱えているのが実情です。
この章では、そうしたBtoB受発注業務がなぜ今「見直しのタイミング」を迎えているのか、その背景とデジタル化の必要性について解説します。
1-1. BtoB受発注業務のよくある課題
「FAXが届いていない」「注文内容を聞き間違えた」「メールを見落としていた」
こうしたミスによるトラブルは、決して珍しくありません。
アナログな受発注手段が使われ続けている背景には、「取引先もそうしているから」「今まではそれでうまくいっていたから」といった慣習があります。
しかし、「今のやり方で特に問題は起きていない」と思っていても、実際には多くの現場で次のような課題が日常的に発生しています。
- 転記や確認のミスが起こりやすい
- 業務が担当者に依存し、属人化している
- 処理に時間がかかり、残業や休日対応を強いられる
- 履歴や進捗状況がわかりづらく、トラブル時の対応に時間がかかる
また、担当者の退職や異動によって業務がブラックボックス化し、「この対応は誰がやっていた?」「前回どう処理した?」と、業務の継続が困難になるリスクすらあります。
1-2. 受発注業務のデジタル化が必要な理由
こうした課題を根本から解消する手段として、受発注システムによるデジタル化が注目されています。
システムで業務を一元管理することで、以下のような効果が期待できます。
- 転記・確認ミスの削減
- 履歴の自動保存で状況把握が容易に
- 受注処理・在庫確認のスピードアップ
- 属人化からの脱却と引継ぎのスムーズ化
- 受注側・発注側双方の業務効率を改善
つまり、受発注の「スピード・正確性・柔軟性」が大きく向上するのです。
これは単なる業務改善にとどまらず、人手不足対策や働き方改革、営業力の強化といった、企業全体の競争力向上にもつながります。
次章では、こうした業務改善につながる受発注システムの具体的なメリットを紹介していきます。
2.BtoB企業が受発注システムを導入するメリット

BtoBの受発注業務をシステム化すると、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?
単に「効率化される」だけではなく、現場の課題解決や業績改善にもつながる効果が数多くあります。
この章では、受発注システムを導入することで得られる主なメリットを5つに整理して紹介します。
2-1. 工数削減と処理スピードの向上
受注処理の自動化により、手入力や転記作業が大幅に減り、作業時間を短縮できます。
たとえば、FAXや電話で届いた注文内容をエクセルに入力し、さらに社内システムに転記するといった「二度手間」「三度手間」が不要になります。
- 手入力や転記作業を削減
- 社内承認や在庫確認のスピードアップ
- 担当者の残業削減や休日対応の軽減
→現場の負担を減らし、限られた人員でも回る体制づくりにつながります。
2-2. 発注ミス・聞き間違いの防止
紙の注文書や電話注文では、「言った・言わない」「見落とした」といったミスがつきものです。
受発注システムを使えば、発注内容がシステム上で明確に記録され、確認画面やアラート機能によって、ミスを防止できます。
- 注文内容の誤記や聞き間違いを防止
- 画面確認・アラート機能で入力漏れを防ぐ
- 対応履歴の保存により後追い対応が可能
→ミスによる手戻りや信頼低下を防ぎ、スムーズな取引が実現します。
2-3. 対応スピードの向上
受発注システムを活用すれば、在庫確認や納期回答など、従来はメールや電話を必要としていたやり取りも、システム上で即時に対応可能になります。
これにより、取引先とのコミュニケーションも円滑になり、満足度の向上にもつながります。
- 営業担当がその場で納期を回答可能
- 倉庫や在庫状況をリアルタイムで確認可能
- 商談機会の損失防止、リードタイムの短縮に貢献
→「待たせない対応」ができることで、顧客満足度の向上にも直結します。
2-4. 発注側の利便性向上
BtoB受発注システムは、受注側の効率化だけでなく「発注する企業側の利便性」も重要なポイントです。
最近ではスマートフォンやタブレットからも操作できるシステムが増え、場所を選ばずに発注できる環境が整っています。
- スマホやタブレットから簡単に発注可能
- カタログ検索やお気に入り機能が充実
- 営業担当による代理注文や入力支援も可能
→発注側にとっても使いやすいことで、受注側の「使ってもらえる仕組み」が整います。
2-5. データの蓄積と業務改善への活用
受注・発注データがすべてシステムに記録されるため、履歴の確認や集計、分析が容易になります。
過去の受注傾向や取引先ごとの発注傾向を分析できるので、業務改善や売上アップの施策にもつなげやすくなります。
- 受注金額や頻度の自動集計
- 取引先ごとの傾向分析
- 属人化の排除とナレッジ共有の促進
→日々の業務を「改善のヒントが見つかる資産」として活用できるようになります。
これらのメリットは、業務効率だけでなく、顧客満足度や経営判断の精度向上にもつながります。
次章では、導入を検討する際に多くの企業が感じる「不安」や「障壁」と、その解消法についてご紹介します。
3.導入前に知っておきたいよくある不安と解消法

受発注システムの導入にあたって、「本当に使いこなせるだろうか」「現場が混乱しないか」といった不安を感じる担当者は少なくありません。
この章では、よくある不安とその解消法を項目別に整理し、導入に向けた一歩を踏み出しやすくします。
3-1. 不安1:「費用が高そう」
不安:
「システム導入って何百万円もかかるのでは?」
「うちの規模でも回収できるのか…」
解消法:
最近では初期費用を抑えてスタートできるパッケージ型受発注システムも多数登場しています。
スモールスタートして、必要な機能だけを使いながら、段階的にカスタマイズを加える方式も有効です。
ポイント:
|
3-2. 不安2:「取引先が使ってくれるか不安」
不安:
「うちはシステムを導入したいけど、発注側がアナログのままだと意味がないのでは?」
解消法:
発注側が使いやすいUI(スマホ/タブレット対応・LINE連携など)や、代理入力機能など「取引先が無理なく使える仕組み」が用意されているシステムを選ぶことがカギです。
また、移行初期はFAX注文も受けられる“併用運用”ができると安心です。
ポイント:
|
3-3. 不安3:「自社フローに合うか不安」
不安:
「うちは商流が少し特殊で、既存の仕組みに合うかわからない」
解消法:
パッケージ型でもカスタマイズに柔軟なサービスを選ぶことで、自社の業務フローにフィットさせることができます。
完全に業務を変えるのではなく、今の業務に合わせられるかを重視しましょう。
ポイント:
|
3-4. 不安4:「現場のITリテラシーが低い」
不安:
「システムが難しそうで、現場のスタッフが使いこなせるか心配」
「PCが苦手というお客様も多いけど大丈夫かな…」
解消法:
UIがシンプルでわかりやすく、かつベンダーによる操作研修・導入支援が充実しているサービスを選びましょう。
「トライアルで実際に触ってみる」のも有効な判断基準です。
ポイント:
|
3-5. 不安5:「導入後のサポートが不安」
不安:
「システム導入後、トラブル時にすぐ対応してもらえるのか?」
解消法:
導入後のサポート体制(QA、チャット、定期訪問など)が明確なベンダーを選ぶことが重要です。
特に「導入初期の立ち上げ支援」があるかどうかを確認しましょう。
ポイント:
|
このように、「導入が不安…」という壁は、正しい選定と支援体制によって乗り越えることができます。
次章では、実際にどんな種類の受発注システムがあり、どう選ぶべきかを整理していきましょう。
4.受発注システムの種類と選び方

受発注業務をデジタル化するにあたって、どんな形でシステムを導入するかは非常に重要です。
ここでは、代表的な3つの開発スタイル(方式)を比較しながら、それぞれの特徴と向いているケースをご紹介します。
【受発注システムの比較表】
比較項目 | パッケージ型 | カスタマイズ開発 | フルスクラッチ開発 |
初期費用 | ◎ 低い | ○ 中程度 | △ 高い |
導入スピード | ◎ 早い | ○ 普通 | △ 遅い |
柔軟性・自由度 | △ 低い | ○ 中程度 | ◎ 高い |
カスタマイズ性 | △ 制限あり | ◎ 可能 | ◎ 自由 |
導入後の運用負荷 | ◎ 少ない | ○ 普通 | △ 高い |
4-1. パッケージ型
特徴:
すでに完成された標準機能を備えており、導入後すぐに使える形式です。
短期間・低コストでのスタートに向いており、最も導入ハードルが低いタイプです。
メリット:
- 短納期・低コストでスタートできる
- 必要最低限の機能が初めから揃っている
- SaaS型のようにクラウドで提供されるケースも多い
デメリット:
- 自社独自のフローには合わない場合も
- カスタマイズには制限があるケースも
向いている企業:
|
4-2. カスタマイズ開発
特徴:
パッケージ型のコア機能をベースに、自社の要件に合わせて機能を追加・改修していく方式です。
柔軟性とスピードのバランスが取れる“中間型”ともいえる存在です。
メリット:
- 必要な機能だけを追加できる
- 自社の業務フローにフィットさせやすい
- 運用しながら段階的に育てていける
デメリット:
- 要件整理や開発期間が必要
- 追加開発に費用がかかることも
向いている企業:
|
4-3. フルスクラッチ開発
特徴:
ゼロから自社専用に設計・開発する方式です。
独自の業務要件や複雑な商流に合わせた最適なシステムを構築できます。
メリット:
- どんな要望にも対応可能
- 既存システムや基幹業務との統合も自由
- 自社の強みや商流に合わせて設計できる
デメリット:
- 高コスト・長期プロジェクトになる
- 内部のIT体制やベンダーとの連携力が問われる
向いている企業:
|
4-4. 選び方のポイント
受発注システムの選定では、単に「高機能なもの」や「価格が安いもの」を選ぶのではなく、自社の業務フロー・商流・目的に合ったものを選ぶことが最重要です。
- 急いで立ち上げたい → パッケージ型
- 自社にぴったりの形に育てたい → カスタマイズ型
- 特殊な業務要件・高度な連携が必要 → フルスクラッチ型
次章では、さらに導入時にチェックしておきたい8つの比較ポイントをご紹介します。
システムを選ぶ際の実務的な視点を確認していきましょう。
5.検討時に必ずチェックすべき8つのポイント

BtoB取引に適した受発注システムの「種類」が見えてきたら、次は「どのサービスを選ぶか」という具体的な検討に進みます。
ただし、単に「機能が多い」や「価格が安い」といった表面的な判断では、自社に合わないシステムを選んでしまう恐れも。
この章では、導入後の後悔を防ぐために、比較検討時に必ずチェックすべき8つのポイントをご紹介します。
5-1. 初期費用・月額費用
最初に確認したいのは、導入時の初期費用と、継続的にかかる月額コストです。
- 初期費用:設定費用・開発費・環境構築など
- 月額費用:利用料・アカウント数に応じた従量課金など
パッケージ型は比較的安価に始められますが、カスタマイズや外部連携を行う場合は追加費用が発生します。
「初期費用とランニングコストのバランス」を見ながら、トータルでのコスト感を掴みましょう。
5-2. 導入期間(スピード)
「いつから使い始められるのか?」という導入スピードも重要です。
- パッケージ型:最短で1〜2週間でスタートできるケースも
- カスタマイズ開発:要件整理を含めて1〜3ヶ月
- スクラッチ開発:半年〜1年規模のプロジェクトになることも
すぐに改善したい業務課題があるなら、導入スピードは最優先の判断材料になります。
5-3. 発注者側のUI・操作性
いくら高機能でも、取引先や現場担当者が使いこなせなければ意味がありません。
- メニューや操作画面はシンプルか?
- スマホやタブレットでも操作しやすいか?
- 説明なしでも迷わず使えるUIか?
UI/UXの使いやすさは、利用率・定着率に直結する重要な評価ポイントです。
5-4. 在庫・商品・注文の一元管理ができるか
BtoB受発注では、以下のような情報を正確かつスピーディに処理できることが求められます。
- 商品マスタ(商品名・型番・価格など)
- 在庫数のリアルタイム反映
- 注文履歴や納期ステータスの可視化
システム導入によって、「見える化」と「属人化の解消」が実現できるかを確認しましょう。
5-5. カスタマイズ対応力
標準機能だけで十分なケースもありますが、実際には自社フローに合わせた調整が必要になることも少なくありません。
- 代理発注や承認フローの追加
- 得意先ごとの価格設定
- 複数倉庫・複数ブランドの対応
こうした現場のリアルな運用に耐えられる柔軟性があるかを確認しておきましょう。
5-6. 既存システム(基幹・在庫・会計)との連携可否
すでに利用している社内システムとAPI連携やCSV連携が可能かどうかは、運用のスムーズさに直結します。
- ERP、販売管理、在庫管理との連携実績があるか
- 双方向連携(読み取り・書き込み)ができるか
連携ができないと、かえって手作業が増えてしまう可能性もあるため、ここは事前に要確認です。
5-7. 導入後のサポート体制(トレーニング・QA)
導入後に「誰が教えるのか?」「困ったときに誰が助けてくれるのか?」は非常に重要です。
- 初期導入支援(オンボーディング)あり?
- 操作マニュアル・FAQは充実している?
- サポート窓口の対応スピードは?
使い続けられる環境が整っているかどうかも、システム選定の大きなポイントです。
5-8. トライアル・お試し環境の有無
実際に操作してみないと、現場との相性はわかりません。
- デモ環境の提供
- 一定期間の無料トライアル
- 機能制限つきの簡易版アカウント
このような仕組みが用意されていると、現場担当者の不安も払拭しやすくなります。
これら8つのポイントをもとに比較・検討することで、導入後に「こんなはずじゃなかった」とならないための意思決定の質が高まります。
次章では、業界ごとに異なるニーズにどう応えるか——業界・業務特性に合わせた「システム選定のコツ」をご紹介します。
6.業界・業務特性に応じたシステム選定のコツ

BtoB取引における受発注システムを選ぶ際に見落としがちなのが、「業界ごとの特性」や「自社の商流・業務スタイル」への適合性です。
どんなに高機能なシステムであっても、自社の業務にフィットしなければ活用されず、現場の負担やコストばかりが増えてしまうことも。
この章では、業界ごとにありがちな受発注フローの特徴と、それに合ったシステム選定の視点をご紹介します。
【業種別特性と必要な機能や対応】
業種 | 特性 | 必要な機能や対応 |
卸業・商社 | 多品種・価格別対応 | バイヤー管理・代理発注・価格別表示 |
メーカー | 製造・在庫連動 | 見積書出力・在庫同期・帳票機能 |
小売 | 現場の使いやすさ | スマホUI・販促連携・画像表示 |
その他共通 | 取引先への配慮 | 使いやすいUI・カスタマイズ性 |
6-1. 卸業・商社:多品種・多拠点の受発注を効率化したい
卸業や商社では、以下のようなニーズがよく見られます。
- 数百〜数千点の商材を取り扱う(商品点数が多い)
- 拠点や営業所ごとに発注元が分かれる
- 取引先ごとに価格や出荷条件が異なる
商品・在庫・注文の一元管理はもちろんのこと、「得意先ごとの価格表示」「代理発注」「在庫連携」といった商流に沿った柔軟な対応が求められます。
選定ポイント:
|
6-2. メーカー:製造・在庫・販売部門をまたいだ業務連携が必須
製造業では、以下のような業務上の特徴があります。
- 受注内容に応じて製造・出荷計画が変わる
- 在庫状況と紐づけた発注調整が必要
- 見積書・提案書など営業資料との連携が求められる
単なる受発注処理にとどまらず、製造・在庫・営業との連携を考慮した設計が不可欠です。
選定ポイント:
|
6-3. 小売業:発注の簡便性と販促連携がカギ
小売業では、スピードとわかりやすさが特に重視されます。
- 現場でスマホやタブレットから発注したい
- 商品画像や販促資料も一緒に見たい
- セールや新商品の案内を同時に行いたい
受発注だけでなく、販促やカタログ連動などの情報発信もあわせて行えるシステムが求められます。
選定ポイント:
|
6-4. 取引先との関係性にも着目を
BtoB取引においては、「自社の都合だけで選んでも使ってもらえない」というのがよくある落とし穴です。
- 長年の商習慣がある相手
- ITリテラシーに差がある
- 発注者側が高齢化している
このような取引先が多い場合は、誰でも迷わず操作できるシンプルな画面設計や、段階的な移行支援が必要です。
選定ポイント:
|
次章では、こうした実際のニーズを踏まえて、「すぐに始められて、業務にフィットしてカスタマイズできる」BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」をご紹介します。
7.BtoBのための受発注システム「WONDERCART」
これまで見てきたように、BtoBの受発注システムを選ぶうえでは、「自社の業務フローに合う柔軟性」と「導入しやすいスピード・コスト」の両立がカギとなります。
WONDERCART(ワンダーカート)は、そうしたニーズに応える “ちょうどいい” ハイブリッド型の受発注システムです。
【WONDERCARTの特長】
特徴 | 内容 |
標準機能が豊富 | 商品管理・在庫管理・注文管理・カテゴリ管理など、BtoBに必要な基本機能を網羅 |
短期間で導入可能 | コア機能はパッケージ化されており、最短2週間から運用開始が可能 |
業務に合わせてカスタマイズ可能 | 下代管理、代理注文、得意先別対応など、柔軟な機能追加が可能 |
取引先に配慮したUI/UX | シンプルで直感的な画面設計により、取引先のITリテラシーを問わず使いやすい |
紙カタログとの連動にも対応 | 印刷会社ならではのノウハウで、カタログとオンライン受注を組み合わせた活用が可能 |
導入サポートも充実 | 要件整理から現場説明資料の作成、運用定着支援までトータルで対応 |
標準パッケージ機能(一部抜粋)
- ダッシュボード:受発注の進捗状況を一覧で可視化
- 商品管理/カテゴリ管理:商品画像・説明文・分類の一元管理
- 在庫管理:在庫数の自動反映・アラート設定
- 注文管理:注文ステータス管理・帳票出力
- バイヤー/サプライヤー管理:得意先・仕入先ごとの個別設定
- CSV一括インポート/エクスポート:商品・在庫・注文データの一括連携
- CMS機能:お知らせ・販促ページの簡易更新にも対応
カスタマイズ対応例(オプション)
- 下代ごとの価格設定機能
- 営業や代理店による「代理注文機能」
- 得意先ごとの専用画面表示/非表示の制御
- 見積書や提案書の自動出力機能
- 紙カタログに連動したQRコード連携オーダー機能
サポート・導入支援もフル対応
- 初回ヒアリングから運用フローの整理まで伴走支援
- 管理者マニュアル・取引先向け説明資料の作成サポート
- トライアル導入・段階的な切り替えプランの設計
- 運用開始後のQA・追加改修にも柔軟に対応
「すぐに始められて、業務に合わせて柔軟に拡張できる」—— そんな理想の受発注システムを探している企業にとって、WONDERCARTは最適な選択肢の一つとなるはずです。
次章では、記事全体のまとめと「最初の一歩」を踏み出すためのアクションをご紹介します。
8.まとめとアクション
BtoBの受発注業務は業種・業界によって異なるため、「一番優れたシステム」ではなく「自社に合うか」が何より重要です。
本記事では比較ポイントや業界別の選定のコツも解説しました。
受発注システムの比較表はこちらです。
比較項目 | パッケージ型 | カスタマイズ開発 | フルスクラッチ開発 |
初期費用 | ◎ 低い | ○ 中程度 | △ 高い |
導入スピード | ◎ 早い | ○ 普通 | △ 遅い |
柔軟性・自由度 | △ 低い | ○ 中程度 | ◎ 高い |
カスタマイズ性 | △ 制限あり | ◎ 可能 | ◎ 自由 |
導入後の運用負荷 | ◎ 少ない | ○ 普通 | △ 高い |
検討時に必ずチェックすべき8つのポイントはこちらです。
|
業種別特性と必要な機能や対応の一覧表はこちらです。
業種 | 特性 | 必要な機能や対応 |
卸業・商社 | 多品種・価格別対応 | バイヤー管理・代理発注・価格別表示 |
メーカー | 製造・在庫連動 | 見積書出力・在庫同期・帳票機能 |
小売 | 現場の使いやすさ | スマホUI・販促連携・画像表示 |
その他共通 | 取引先への配慮 | 使いやすいUI・カスタマイズ性 |
本記事を参考にしていただき、自社にぴったりの受発注システムをみつけてください。
新日本印刷の「WONDERCART(ワンダーカート)」では、誰にでも使いやすいUI設計と、導入から運用までの丁寧なサポートを通じて、取引先とのスムーズな受発注体制づくりを支援しています。
#受発注システム #btob


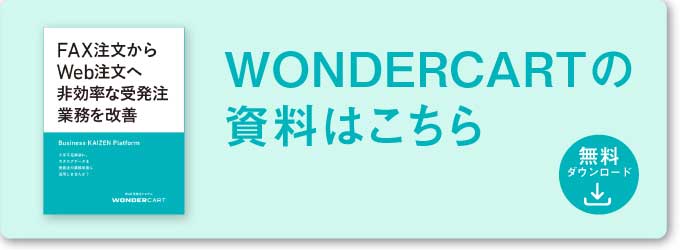

コメント