
「あの商品、またお願い」
「この前と同じのでいいから」
BtoB取引の現場で、顧客からそんな言葉をかけられてヒヤッとした経験はありませんか?
何となく思い当たる商品があるものの、カタログには載っていない。
仕様書や品番もはっきりせず、結局は過去の注文履歴を手作業で探し直すことに……。
営業担当や受注業務の現場では、こうした「記憶に頼ったやりとり」が日常的に行われています。
その場しのぎでなんとか対応できたとしても、長期的に見るとその業務は再現性に乏しく、属人化やミスの温床になっていくのが実情です。
本記事では、
- なぜ記憶頼みの受注が日常化してしまうのか
- 現場にどのような負担やリスクをもたらしているのか
- データに基づいた再現性ある業務フローへ変えるにはどうすればよいか
という観点から、商品情報の整備や業務フローの改善ポイントを解説します。
あなたの現場でも、いつの間にかブラックボックス化していた業務を、見えるかたちで「誰でも、正確に」運用できるようになるヒントがきっと見つかるはずです。
目次
1. なぜ記憶に頼った受注が生まれるのか

BtoBの受注業務では、
「この前と同じでいいです」
「去年お願いしたあの商品をもう一度」
といったやりとりが頻繁に交わされます。
一見すると、スムーズな顧客対応のようにも感じられますが、実際には大きなリスクを孕んだ運用と言えます。
というのも、そうしたやりとりの裏には、「誰が」「いつ」「どんな情報をもとに」対応しているのかが明文化されていないことが多く、注文処理が特定の担当者の記憶に依存してしまっているからです。
たとえば、こんなケースに心当たりはないでしょうか?
- 電話を取った担当者が、過去のやりとりを思い出しながら品番をメモする
- メールの履歴をさかのぼって、注文内容を探し出す
- 前回注文時の紙の控えを倉庫で探すために、担当者が席を外す
- 「たぶんこれだったと思う」という曖昧な情報で出荷が進む
こうした対応は、一時的には業務を回すことができても、誰かが休んだ日や、異動・退職があったときに大きな混乱を招く原因になります。
また、曖昧なやりとりの中で、商品の色やサイズ、仕様などにズレが生じれば、トラブルや再対応のコストが発生することになります。
なぜ、こうした記憶に頼った業務が生まれてしまうのでしょうか。
その背景には、商品情報の管理が体系化されておらず、必要な情報が「担当者の頭の中」や「個人フォルダ」にとどまっているという構造的な課題があります。
たとえば、商品に関する情報が
- 営業部ではエクセルで管理されている
- 商品企画部ではPDFで保存されている
- 製造部には社内システム上にしか情報がない
といったように、部門ごと・担当者ごとに情報の所在や形式がバラバラなケースは少なくありません。
このような状況では、「知っている人が対応するのが一番早い」という判断が優先され、業務の属人化が進んでいきます。
そしてその属人化がさらに、「誰も仕組みを整えようとしない」状態を招き、記憶頼みの受注処理が定着してしまうのです。
次章では、こうした運用がもたらす実際のリスクについて、さらに深掘りしていきます。
日々の現場では見えづらい「ひと手間」や「確認作業」の積み重ねが、どれほど業務全体に影響を及ぼしているのかを整理していきましょう。
2. 見えない「ひと手間」が現場を圧迫する
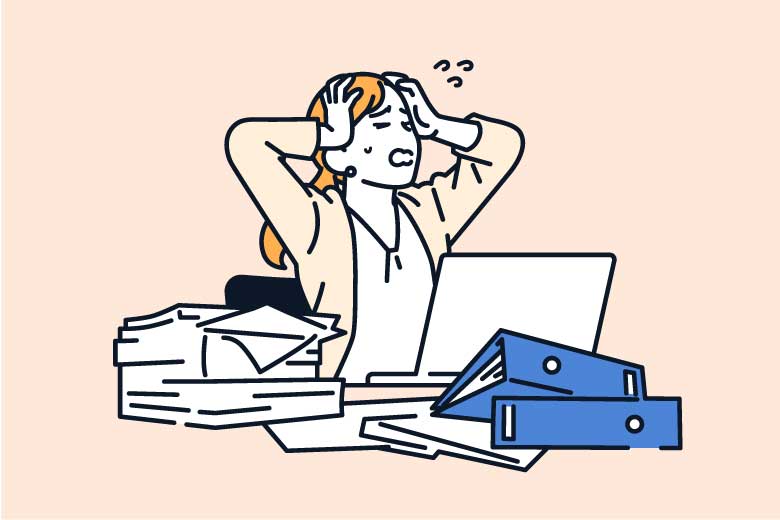
記憶に頼った受注対応が常態化している現場では、表面上は問題なく業務が回っているように見えても、その裏で数多くの「ひと手間」が積み重なっています。
このひと手間は、関わる人の時間や集中力をじわじわと奪い、気づかないうちに大きな負担となっているケースが少なくありません。
こうした確認作業、あなたの現場でも起きていませんか?
- 顧客から電話で問い合わせが来た際に、該当商品の品番を確認するためにエクセルファイルを開き、社内システムと照らし合わせる
- 前回と同じ条件でいいと言われたけれど、「前回」がいつだったのかを社内チャットやメールで確認し直す
- 自分が対応した案件ならわかるが、別の担当者が過去にやりとりした情報は、ファイルの場所や書式もバラバラで探すのにひと苦労
こうした確認は、決して目立つ作業ではありません。
ただし、1回あたりにかかる時間は数分から十数分程度でも、1日に何件も発生すれば、積み重なる負荷は膨大になります。
また、情報を探すだけでなく「本当にこの情報で合っているのか」を裏付けるための確認作業も発生し、社内の他部署に問い合わせたり、関係者に再確認を取るといった手間も発生します。
このような状況が続くと、次第に以下のような負の連鎖が起こりやすくなります。
- 確認作業に時間を取られ、対応スピードが落ちる
- 担当者によって業務の精度にバラつきが出る
- 忙しさゆえに確認を飛ばしてしまい、誤出荷や納期トラブルが発生する
- ミスのフォローに時間を使い、さらに業務が逼迫する
このような事態が起きると、最前線で対応する担当者は精神的なプレッシャーを抱えることになります。
顧客からの信頼を維持するために、急ぎで対応しなければならない、でもミスは許されない──そんな緊張感の中で、1つ1つの業務に気を張り続ける状態が常態化してしまいます。
さらに、こうした手間が積み重なる業務には、もうひとつの問題があります。
それは、「誰がどこでどんな工夫をしているか」が可視化されにくいため、改善に踏み出すきっかけが見えにくくなるという点です。
日々の非効率が、現場で「当たり前」になってしまうと、
「これはこういうものだから仕方ない」
「今さら変えるのはかえって大変だ」
といった空気が根付き、業務改善への意識そのものが薄れていってしまいます。
このように、見えないひと手間は単なる作業の手間にとどまらず、現場の疲弊や判断ミス、そして業務改善を阻む無意識の壁につながっていくのです。
では、こうした手間を解消するにはどうすればよいのでしょうか?
次章では、その背景にある「情報の散在」と「共有の難しさ」に焦点を当てながら、属人化の構造について整理していきます。
3. 受注業務の属人化が招く非効率とリスク

「〇〇さんしかわからないから」
「前回も担当していたし、今回もお願い」
そんな言葉が社内で頻繁に聞かれるようになったら、それは業務が属人化しているサインかもしれません。
属人化とは、特定の人しか業務の全体像や処理方法を把握しておらず、その人がいなければ仕事が進まない状態のことを指します。
BtoB取引の現場では、商品に関する情報管理が特定の人の記憶頼りになっていることが少なくありません。
その結果、商品情報の確認ややり取りに時間がかかり、業務全体の効率を下げてしまいます。
特に「品番」「仕様」「条件」といった、取引に必要なデータが複数のファイルやツールに散らばっている場合、それらを理解・把握している人物にしか対応ができず、情報の受け渡しや確認のたびに時間や手間が発生します。
たとえば——
- 商品の品番が複数存在し、どれが最新版かは〇〇さんに確認しないとわからない
- 顧客ごとの特別単価や仕様変更の履歴が、担当者の個人メールにしか残っていない
- 在庫の確認ルートが部署ごとに異なり、人を介さないと情報が得られない
こうした状況では、業務を引き継ごうとしても十分な情報が残っておらず、処理の質が落ちたり、ミスが発生したりするリスクが高まります。
さらに、属人化の弊害は単なる作業効率の低下にとどまりません。
属人化はこのようなリスクをもたらします。
- 業務の再現性が失われる
「過去にどう対応したか」が明文化されていないと、同じ内容の注文でも都度対応が異なってしまい、品質にばらつきが出ます。 - トラブル時の対応に遅れが出る
問い合わせやクレームが発生した際、関係者が不在だと内容を把握できず、謝罪や対応が後手に回る可能性があります。 - 新任者の教育コストが増える
業務がマニュアル化されていないため、新しい担当者は「仕事のやり方」をゼロから手探りで覚える必要があり、立ち上がりに時間がかかります。 - 現場の緊張感や負担が高まりやすい
属人化している担当者には問い合わせが集中し、周囲も「〇〇さんがいないと進まない」と依存する構図ができてしまいます。
これらはすべて、商品情報が一元化・共有されていないことに起因します。
情報が見える化されておらず、誰でも同じように対応できる仕組みがない状態では、自然と「知っている人」「できる人」に業務が集中してしまうのです。
現場の効率化を目指すなら、このような属人化の構造を解きほぐすことが不可欠です。
そのためには、「人に聞く」運用から「情報にアクセスできる」運用への転換が求められます。
次章では、その転換を実現するための具体的な取り組みとして、「商品情報の一元化」に焦点を当てます。
業務を効率化し、誰もが迷わず対応できる環境をどう整えていけばよいのか、現場視点で整理していきましょう。
4. 商品情報の一元化がもたらす変化
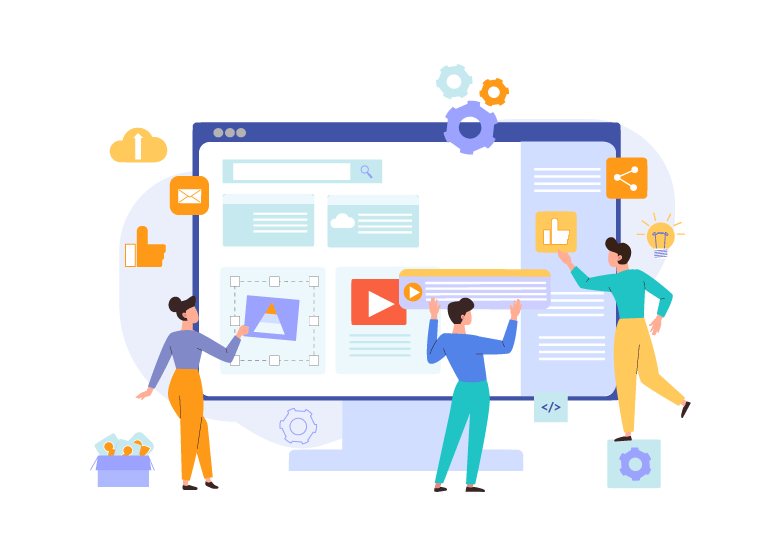
業務の属人化や確認作業の手間を解消するには、商品情報の「一元化」が不可欠です。
一元化とは、取引に必要な情報を誰もが迷わずアクセスできるよう、ひとつの場所に集約・整理することを指します。
重要なのは、単に情報をどこかに集めるということではありません。
本当に意味のある一元化とは、情報の「内容」「形式」「更新ルール」「アクセス権限」まで含めて、全員が迷わず使えるように整えることです。
4-1. 一元化されていない現場で起こりがちなこと
一元化の必要性は頭では理解していても、「何が問題なのか」がはっきり見えていないケースも少なくありません。
ここでは、商品情報がバラバラに管理されている現場で、実際に起こりがちな混乱や非効率の例を挙げてみましょう。
- 「営業用エクセル」と「製造管理システム」で品番表記が違う
- 顧客向け資料と社内資料で商品名が異なる
- 単価や仕様の改訂がメールでしか共有されておらず、反映漏れが起きる
- 在庫の有無を確認するたびに他部署へ電話やチャットで確認が必要
こうした状況では、情報のズレを補うために都度「人」が動くことになり、ミスや時間ロスの原因となります。
また、情報の出どころが不明確だと、どのデータが正しいのか判断できず、やりとりが止まることもあります。
4-2. 一元化による業務改善の具体例
商品情報をシステム上で一元管理できるようになると、業務の流れは大きく変わります。
- 過去の注文履歴から、ワンクリックで商品情報を呼び出せる
- 顧客ごとの仕様・価格条件が自動で紐づく
- 在庫状況がリアルタイムに確認できる
- 誰が対応しても、同じ帳票が、同じ書式で出力できる
つまり、一元化によって「特定の人に聞かないとわからない」状態を脱却し、業務を再現性のある仕組みに変えることができるのです。
この変化は、単なる業務効率の向上にとどまりません。
確認のたびに人に頼る必要がなくなることで、社内のコミュニケーション負荷が減り、担当者の心理的ストレスも軽減されます。
さらに、情報が整理されていれば、新しいメンバーへの引き継ぎもスムーズになり、教育コストも削減されます。
次章では、こうした一元化をどうやって実現するのか。
業務フローを変えるときにぶつかる「運用の壁」をどう乗り越えるかを考えていきます。
5. 一元化はどう進める?運用に落とし込むための工夫

商品情報の一元化が重要だとわかっていても、
「どこから手をつければいいのか見当がつかない」
「結局、元に戻ってしまいそう」
と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
実際、日々の業務に追われる中で、新たな仕組みをつくる余裕はなかなか生まれません。
また、せっかく整備しても、現場で活用されなければ意味がありません。
そこでここでは、「いかに無理なく、業務の中に一元化を落とし込むか」に焦点を当て、運用につなげるための現実的なアプローチを3つご紹介します。
5-1. 一気に進めようとしない
まず重要なのは、「すべてを一度にやろうとしない」ことです。
商品情報の一元化は、システム導入やルール策定といった大きなプロジェクトに見えるかもしれませんが、最初は小さな改善からでも始められます。
たとえば、次のような取り組みが有効です。
- よく使う商品10品だけでも、社内で使う品番・名称・仕様を統一する
- 「注文時に必ず確認する項目」のチェックリストを作る
- 見積書や伝票のテンプレートを共通化し、表記ルールを揃える
最初から完璧な状態を目指すのではなく、「手が届く範囲で共通のルールを持つ」ことが、業務の標準化・一元化への第一歩になります。
5-2. 情報の出どころを明確にする
属人化した業務の多くは、「誰が何を管理しているのか」が不透明で、情報の責任範囲が曖昧です。
一元化を進めるには、まず「この情報は誰が正確に把握しているべきか」を明らかにする必要があります。
たとえば、
- 単価の決定は営業部、在庫は製造部、仕様変更は企画部──と役割を分ける
- 情報の更新があったときに「どこに」「どう反映するか」ルール化する
- 定期的な情報棚卸しや見直しのタイミングを決めておく
こうした情報の責任分担を明文化することで、「誰かに聞かないとわからない」状態を防ぎやすくなります。
5-3. 現場にとって使いやすい仕組みにする
「情報を集約したけれど、誰も使ってくれない」
これは、情報の一元化にありがちな失敗です。
システムやルールはあっても、現場の使い勝手を無視した仕組みでは、定着しないまま形骸化してしまいます。
- 入力の手間が少ない
- 検索しやすく、探したい情報がすぐ見つかる
- スマホやタブレットでもアクセスしやすい
現場視点での「使いやすさ」を重視することで、一元化は初めて「運用できる仕組み」として根づきます。
次章では、こうした運用が現場に定着するために必要な「仕組みの使われ方」について掘り下げていきます。
6. 現場が使える仕組みをつくるには

商品情報の一元化を進めるうえで見落とされがちなのが、「現場で本当に使えるかどうか」という視点です。
どんなに優れたシステムでも、現場の実情に合っていなければ、うまく活用されず、次第に形骸化していってしまいます。
一元化の仕組みを現場に根づかせるには、導入するツールや設計思想そのものに「現場目線」が必要不可欠です。
6-1. 入力・更新しやすいことが最優先
商品情報の一元化では、正しいデータを「蓄積する」だけでなく、日々の業務の中で「使われる」ことが重要です。
そのためには、情報の入力や更新が誰にとってもわかりやすく、無理のないフローである必要があります。
たとえば――
- フォーマットが複雑すぎて、入力に時間がかかる
- 更新ルールが共有されておらず、記入方法が人によってバラバラ
- 更新自体が一部の担当者に任されていて、反映にタイムラグがある
こうした状態では、せっかくの一元化も「情報が信用できない」「使いにくい」と感じられてしまい、運用が続かなくなってしまいます。
入力や更新のしやすさは、「現場で使われ続ける仕組み」づくりの第一条件です。
定期的に見直しが行われ、情報が常に最新の状態に保たれてこそ、一元化の効果が発揮されます。
6-2. 「見る人」「使う人」に合わせた構造にする
商品情報とひとくちに言っても、必要な情報は立場によって異なります。
たとえば、営業が知りたいのは顧客への提案に必要な情報であり、製造現場では寸法や材料、製造条件が重視されます。
誰にでもすべての情報を見せる必要はありません。
むしろ、役割に応じた情報の整理や出し分けを意識することで、必要な人に、必要なタイミングで、必要な情報を提供できる仕組みになります。
- 営業には、販売単価・提案資料・納期目安
- 受注担当には、品番・仕様・在庫情報・顧客ごとの条件
- 製造には、図面・工程・材料情報
このように、利用シーンやユーザーに応じた構成を設計することで、情報の「見やすさ」「使いやすさ」が格段に向上します。
6-3. はじめての人でもすぐに使える
業務が属人化しないためには、「誰でも対応できる状態をつくる」ことが何より重要です。
そのためにも、操作が直感的で、マニュアルがなくてもすぐに使える仕組みであることが望ましいです。
チェック項目が整理されていて、画面上のナビゲーションも明快。
検索機能や絞り込み条件が簡単に使えるなど、「初めて使う人でも迷わない設計」なら、担当者が変わっても業務の品質が維持されます。
属人化を防ぐための仕組みは、育成コストの削減や引き継ぎミスの防止にもつながります。
次章では、「現場で使える仕組みづくり」を支えるツールとして、BtoB受発注業務の改善に貢献する「WONDERCART」をご紹介します。
実際にどのような視点で開発され、どのように業務に定着していくのか──現場のリアルに即した解決策を探っていきましょう。
7.「WONDERCART」で実現する商品情報の一元化
商品情報の一元化は、ただ情報を集めて見える化するだけでは不十分です。
現場で日々使われ、正確な情報に誰もがアクセスできる、生きた仕組みとして機能することが重要です。
とはいえ、「使い勝手が悪くて現場に定着しなかったら…」「取引先にも使ってもらえるか心配…」そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこでご紹介したいのが、BtoB受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」です。
7-1. 発注側・受注側の両方に寄り添った設計
WONDERCARTは、50年以上にわたり業務用カタログ制作の現場で蓄積されたノウハウをもとに開発された、受発注業務のためのクラウドサービスです。
BtoB取引の発注側・受注側それぞれの実情に寄り添った設計により、取引関係者すべてが使いやすいUIと操作フローを実現しています。
たとえば──
- 発注側には、商品カテゴリや仕様での絞り込み・検索機能を搭載し、目的の商品にすぐたどり着ける設計に。
- 受注側には、注文内容の自動整理や帳票出力機能が用意されており、確認作業や転記ミスのリスクを抑える構成となっています。
こうした双方向の配慮によって、受発注業務のスムーズな運用を下支えします。
7-2. 現場の負担を軽減する業務効率化の機能
WONDERCARTには、日々の受注業務を仕組み化するためのさまざまな機能が搭載されています。
その一つひとつが、現場の「記憶頼み」や「確認作業の手間」を減らすために設計されています。
- 商品情報の一元管理
商品ごとの仕様・単価・在庫情報をシステム上でまとめて管理し、情報を探し回る必要をなくします。確認にかかっていた時間を大幅に短縮できます。
- 帳票の自動出力
見積書・納品書・請求書などを、テンプレートに基づいてクリック一つで出力可能。記入ミスや転記ミスを防ぎ、帳票の品質を標準化できます。
- 注文履歴の検索
顧客単位・商品単位で過去の注文内容を検索できるため、「この前と同じで」という曖昧な依頼にもスムーズに対応できます。
- 社内外の情報連携
社内の営業・事務担当間のやりとり、さらには取引先との情報共有もクラウド上で完結。確認や返信の手間を最小限に抑えます。
これらの機能によって、属人化や手戻りのリスクが抑えられ、「誰が対応しても同じ品質」を保つ受注体制へと移行できます。
7-3. 柔軟な導入設計で、自社にフィットする仕組みへ
WONDERCARTは、導入時の要件や業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。
たとえば──
「まずは一部商品から始めたい」
「業務に慣れたあとで機能を段階的に追加したい」
といったニーズにも対応できるため、初めての方でもスモールスタートで無理なく導入を進められます。
操作も直感的で、マニュアルがなくてもすぐに使いこなせる仕様。
属人化しにくい設計だからこそ、担当変更や増員時の教育コストも抑えられます。
商品情報の確認や管理を「経験のある人」に頼り続ける受注体制は、どうしてもミスや業務停滞のリスクを抱えがちです。
WONDERCARTは、そうした問題に向き合い、「記憶ではなく、正確なデータに基づいた受注業務」へと変えるための仕組みを提供します。
属人化を防ぎ、誰が対応しても同じ品質で受注できる──それは、安心して任せられる体制を築く第一歩です。
「WONDERCART」は、記憶頼みの受注業務を脱却し、誰もが同じ品質で対応できる仕組みを無理なく実現するツールです。
情報を「探す」から「使える」へ──。その変化は、業務の再現性と生産性を高める大きな一歩になるはずです。
\まずは資料からご覧ください/
8.まとめ:記憶頼みの受注を「仕組み」で変える
顧客からの「この前と同じでいいから」という一言に、過去の記憶をたどって商品を思い出そうとする——そんな対応が、BtoBの現場では当たり前になっているかもしれません。
しかし、それは業務が属人化し、商品情報が整理されていないサインでもあります。
本記事では、
- なぜ記憶に頼った受注が生まれてしまうのか
- その裏で積み重なる「見えないひと手間」
- 商品情報の分散が生む属人化と業務リスク
- 一元化によって業務がどう変わるのか
- 現場で定着させるための運用の工夫
- 受発注業務を支える仕組みとしてのWONDERCARTの特長
といった観点から、商品情報の整理・共有による業務改善の可能性を探ってきました。
属人化や確認作業に悩む日々を、「仕組み」で変えることは十分に可能です。
小さな取り組みからでも、「誰でも迷わず対応できる」状態をつくっていくことで、業務の安定性と生産性は大きく変わっていきます。
顧客対応の精度を「記憶」ではなく「仕組み」で支える。
その積み重ねが、属人化を防ぎ、ミスを減らし、現場に余裕を取り戻します。
今こそ、「情報の見える化」と「共通のルールづくり」から、変化の一歩を踏み出してみませんか?
\情報の一元化の第一歩/
#商品情報 #一元化


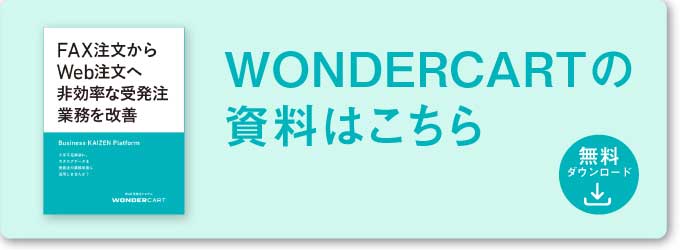
コメント