
業務のデジタル化が進むなか、受発注システムの導入は、今や多くの企業にとって欠かせない選択肢となりつつあります。
特に、取引先とのやりとりが多い商社・卸売業、仕様や部品が複雑な製造業、在庫回転が早い小売業などでは、「受発注の精度」「スピード」「情報共有のしやすさ」が業務効率に直結します。
しかしその一方で、こうした声も少なくありません。
「導入したけど、現場が使いこなせていない」
「結局、取引先はFAXのまま……」
「導入コストに見合う効果が感じられない」
受発注システムは、単に「便利そうだから」「おすすめだったから」という理由だけで選んでしまうと、かえって混乱を招くこともあります。
大切なのは、自社の業務に合うシステムを選び、適切に運用することです。
そこで本記事では、導入を検討中の方に向けて、受発注システムのおすすめタイプを比較・整理しながら、選び方のポイントをわかりやすく解説します。
ランキング形式ではなく、「業界」「業務フロー」「導入目的」といった軸から見たタイプ別の比較にフォーカスし、導入の失敗を防ぐヒントをお届けします。
目次
1.いまさら聞けない受発注システムの基本

受発注業務のデジタル化が進むなか、「そろそろ受発注システムを導入すべきだろうか」と考える企業が増えています。
FAXや電話、紙の発注書でのやりとりは、記入ミス・確認作業の手間・業務の属人化など、さまざまな非効率を引き起こしがちです。
その解決策として注目されているのが、受発注システム。
でも、そもそも「受発注システムとは何か」「どんな機能があるのか」「なぜ導入する企業が増えているのか」——実はよくわからない、という方もいるのではないでしょうか。
この章では、まず受発注システムの基本を丁寧におさらいしながら、導入のメリットや機能についてわかりやすく解説します。
1-1. そもそも受発注システムとは?
受発注システムとは、企業間の発注・受注のやりとりをWeb上で効率化する仕組みです。
取引先が商品を選んで注文し、自社がそれを受け付ける——その一連の流れを、FAXや電話ではなくオンラインで完結できるようにするのが主な役割です。
システム上で注文内容がデータとして記録されることで、転記ミスや確認漏れを防ぎながら、業務をスピーディに進行できます。
多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組む今、受発注システムはBtoBの取引でも定番になりつつあります。
1-2. 受発注システムでできることって?
受発注システムに搭載されている機能は製品によって異なりますが、以下のような機能が基本となります。
1-2-1. 商品管理:商品情報の登録・表示もシステムで簡単に
商品の名称、品番、価格、在庫数、画像、説明文などを一元管理できる機能です。
エクセルや紙のカタログでは更新のたびに差し替えが必要ですが、システム上で商品情報を常に最新の状態に保てるため、正確な情報を取引先に提供できます。
また、取引先ごとに商品表示を制限する機能を活用すれば、「A社にはこの商品だけを見せる」「B社にはこの商品も見せる」といった運用も可能になります。
商品提案やプロモーションにも柔軟に対応できるのが、この機能の魅力です。
1-2-2. 注文管理:発注・受注のやりとりを一元管理
取引先からの注文情報をリアルタイムで受け取り、社内での処理状況を管理する機能です。
注文ステータス(受付済/出荷待ち/納品済など)の管理や、社内での承認フローの設定にも対応できるシステムが多く、属人化の防止や社内コミュニケーションの効率化にもつながります。
また、注文履歴や注文者ごとの傾向も把握しやすくなるため、対応ミスの削減や業務引き継ぎのスムーズ化にも効果があります。
複数の部門が関与するような業務フローにも適応しやすいのが特長です。
1-2-3. 在庫管理:在庫の見える化で「売り逃し」や「在庫切れ」対策に
在庫管理システムや倉庫データと連携し、在庫状況を取引先に表示する機能です。
注文後に「在庫切れでした」と伝えることがなくなり、取引先の信頼を損なうリスクを減らせます。
また、自社側でも受注残や出荷予定数を把握しやすくなり、在庫回転の最適化にも役立ちます。
特に商品ごとの品番やバリエーションが多い業種(=SKU数が多い業種)や、日々の在庫変動が大きい商材を扱う企業には不可欠な機能といえるでしょう。
1-2-4. 帳票出力・通知など、便利なプラスα機能も
上記の基本機能に加えて、受発注システムには導入や運用の負担を軽減してくれる補助機能が多数用意されています。
これらはなくても運用できるかもしれませんが、現場での「使いやすさ」や「続けやすさ」に大きく関わる要素です。
たとえば以下のようなものがあります。
- 発注書・納品書の自動出力
帳票をPDFなどで即時出力し、メール添付での送付にも対応。
- CSV出力・インポート
既存の基幹システムや会計ソフトとの連携を容易にし、転記作業を不要に。
- 通知機能(メール/チャット連携)
注文完了や出荷情報を自動通知。人が確認する手間を削減。
- スマートフォン/タブレット対応
外出先や現場でも使いやすく、利用定着を促進。
こうした機能の有無は、導入後の業務効率に大きな差を生むこともあります。
1-3. なぜ導入する企業が増えているのか?そのメリットとは
受発注システムは単なるツールではなく、現場の困りごとに直接作用する実用的な仕組みです。
導入によって、以下のような業務課題の解決が期待できます。
- 転記ミス・入力ミスの防止
手書きや口頭伝達に比べて、圧倒的に正確なデータ入力が可能になります。
- やりとりのスピードアップ
確認・返信・承認といった各ステップがオンラインで完結し、処理が迅速に。
- 業務の属人化を解消
誰が見ても情報が整理された状態になり、担当者不在時も対応しやすくなります。
- 取引先対応の効率化
よくある問い合わせ(「あの商品、まだありますか?」「納期いつですか?」)に都度対応しなくても、システム上で確認できます。
このように、現場でよくある負担やトラブルを軽減できることが、受発注システムが広く支持されている理由のひとつです。
ただし、すべての企業に同じシステムが合うわけではなく、目的や業種ごとに適したおすすめのタイプがあります。
次章では、導入目的や自社の業務に合わせた「おすすめタイプ」について、3つのパターンに分けて解説します。
2.どのタイプが自社に合う?受発注システムのおすすめ比較
タイプ | 導入スピード | コスト | 柔軟性 | 向いている企業 |
パッケージ型 | 早い | 低い | 低い | 中小企業・初導入の企業におすすめ |
カスタマイズ開発型 | 中程度 | 中程度 | 高い | 業務に合った設計が必要な企業におすすめ |
フルスクラッチ開発型 | 遅い | 高い | 非常に高い | 完全独自仕様が必要な大企業におすすめ |
受発注システムを導入するにあたって、まず悩ましいのが「どのシステムを選べばいいのか」という点です。
インターネットで検索すると、多種多様な製品やサービスが並び、「ランキング」「比較表」「〇〇選」といった情報があふれていますが、人気があることと自社に合うことは必ずしも一致しません。
そこでこの章では、受発注システムを「3つのタイプ」に分類し、それぞれの特徴や向いている業種をわかりやすく整理します。
製品ごとの紹介にとどまらず、「どのタイプが自社に合うのか」を見極めるための考え方をご紹介します。
2-1. すぐに使えてコスパも良好:パッケージ型

パッケージ型とは、あらかじめ機能や画面構成が構築されていて、契約後すぐに使い始められる受発注システムのこと。
クラウドサービス型で提供されることが多く、導入期間は数日〜数週間程度とスピーディ。
機能も「注文管理」「在庫表示」「帳票出力」など、基本的なものはあらかじめ搭載されています。
【 パッケージ型がおすすめなのはこんな企業】
- はじめて受発注システムを導入する企業
- 限られた予算・リソースで運用したい中小企業
- 特殊な業務要件が少ない商材(例:単品商品が中心)を扱う企業
操作マニュアルやヘルプも整っているため、現場への定着率も比較的高くなりやすい点も魅力です。
2-2. 自社仕様にあわせて柔軟に設計:カスタマイズ開発型

業務に特有の処理がある、既存システムとの連携が必要、社内フローが複雑——そんな企業におすすめなのが「カスタマイズ開発型」の受発注システムです。
これは、ベースとなるパッケージやフレームワークを元にしつつ、自社の業務に合わせて必要な部分を柔軟に追加・変更していく開発スタイルです。
【カスタマイズ開発型がおすすめなのはこんな企業】
- 複数部署をまたぐ受発注業務がある
- オプション設定・仕様変更が頻繁な商材を扱っている
- 会計システムや生産管理システムなどとの連携が必要
開発期間は数ヶ月程度になることもありますが、コストを抑えながら業務フローにフィットするシステムが構築できるのが最大の強みです。
2-3. ゼロから作る完全オリジナル:フルスクラッチ開発型

フルスクラッチ型とは、完全にゼロからプログラムを組んで、受発注業務に特化した独自システムを構築する方法です。
仕様も画面もすべてをゼロから設計できるため、自社に最適な仕組みを自由に作れる一方で、構築までに時間とコストがかかるのが特徴です。
【フルスクラッチ開発型がおすすめなのはこんな企業】
- 取引規模・商品数が膨大で、既存システムでは対応しきれない
- 高度な権限管理や自社独自の承認フローが求められる
- グループ企業間で統合的に受発注を管理したい
費用や開発期間はある程度かかりますが、自社特有のルールや業務フローをそのまま反映したシステムを構築したい場合には、フルスクラッチ開発を検討する必要があります。
この章では、「パッケージ型」「カスタマイズ開発型」「フルスクラッチ開発型」の3タイプを紹介しました。
製品選びというと、どうしてもどれが一番有名か、人気か、に目が向きがちですが、実際のところ、自社の規模や業務フロー、取引先の状況に応じて適したタイプはまったく異なります。
次章では、これらのタイプをどう選択するべきか、導入時に見るべき5つの判断基準について詳しく解説していきます。
\パッケージ型とカスタマイズ開発のハイブリッド/
3.失敗しないために見ておきたい5つのチェックポイント

受発注システムのタイプを理解したら、次は「どの製品が自社にフィットするか」を見極めるステップです。
選定の段階でよくあるのが、「機能が多そうだから」「有名だから」だけで選んでしまい、現場に定着しないというケース。
本章では、受発注システム選びで見落とされがちな5つのチェックポイントを整理し、「自社に合った」システムを選ぶための視点をお伝えします。
3-1. 取引先が迷わず使えるか:UI・操作性のチェック
受発注システムは自社だけでなく、取引先(得意先・代理店・店舗など)も使うツールです。
そのため、「誰でも直感的に使える画面かどうか」「誤操作しにくい設計になっているか」は最優先で確認したいポイントです。
とくにITリテラシーが高くないユーザーが多い業種では、ログイン~注文完了までの導線が複雑すぎると利用が定着しません。
「発注したいのに、どうすればいいか分からない」と感じさせてしまうUIは、せっかく導入しても活用されにくくなってしまいます。
| 選定のポイント:取引先の誰が使うのかを具体的にイメージし、デモ画面で「初見でも操作できそうか」をチェックしましょう。 |
3-2. 自社の業務フローにフィットするか
導入後に「思っていたよりも業務に合わなかった」と気づくケースも少なくありません。
たとえば、注文ごとに上長の承認が必要だったり、発注単位が独自だったりといった社内のルールや業務のクセが、パッケージの標準仕様に当てはまらないことがあります。
特に注意したいのは、既存のエクセルや紙の帳票と大きく仕様が違う場合です。
現場が混乱し、むしろ非効率になる恐れもあります。
| 選定のポイント:ベンダーに相談する前に業務フローを図に書き出し、どの工程がシステムで代替できるかを整理しておくと、システムのフローと比較しやすい。 |
3-3. 初期費用とスモールスタートのしやすさ
大規模な一括導入には、多額の初期投資と社内調整が必要です。
一方で、小さく始めて段階的に広げていく「スモールスタート」型の導入なら、負担を抑えながら現場への浸透を図ることができます。
たとえば「まずは得意先10社のみで試す」「社内では1部署だけで先行導入する」といった方法が有効です。
小さく始めることで、初期段階で課題を見つけやすくなり、本格導入もスムーズに進められます。
選定のポイント:段階導入ができるか/初期設定の自由度は高いか、を確認。 |
3-4. サポート体制と運用のしやすさ
「導入後の問い合わせ対応が不十分」「設定変更のたびに追加費用が発生する」——こうした声は、受発注システムの乗り換えを検討する企業からよく聞かれます。
どれだけ良い機能があっても、運用がうまくいかなければ、その価値を十分に発揮できません。
「導入後のトラブル対応が速いか」「質問しやすいサポート窓口があるか」「社内で設定を調整できるか」といった点も、初期段階で見極めたいポイントです。
| 選定のポイント:FAQやチャットサポートの充実度/マニュアルの分かりやすさ/担当者のサポート対応力をチェック。 |
3-5. セキュリティ・将来の拡張性
取引データを扱う以上、セキュリティ対策は不可欠です。
SSL暗号化やIP制限などの基本機能に加え、ログイン履歴の記録やアカウントの権限管理ができるかも確認しましょう。
さらに、将来的に機能を追加したり、他システムと連携できる拡張性も重要です。
たとえば「まずは小さく始めて、あとから他部署にも広げたい」「将来的に他のシステムと連携させたい」といったニーズにも対応できる仕組みかどうかを確認しておくと、あとから無理なく運用を広げていけます。
| 選定のポイント:セキュリティ対策の実装状況/API連携の可否/ユーザー数・機能拡張の柔軟性 |
次章では、これらの基準をもとに、業界別におすすめの受発注システムタイプをさらに詳しく見ていきます。
では次に、業界ごとの特性を踏まえながら、どのタイプの受発注システムが適しているのかを整理していきましょう。
4.業界によって違う、おすすめの受発注システム
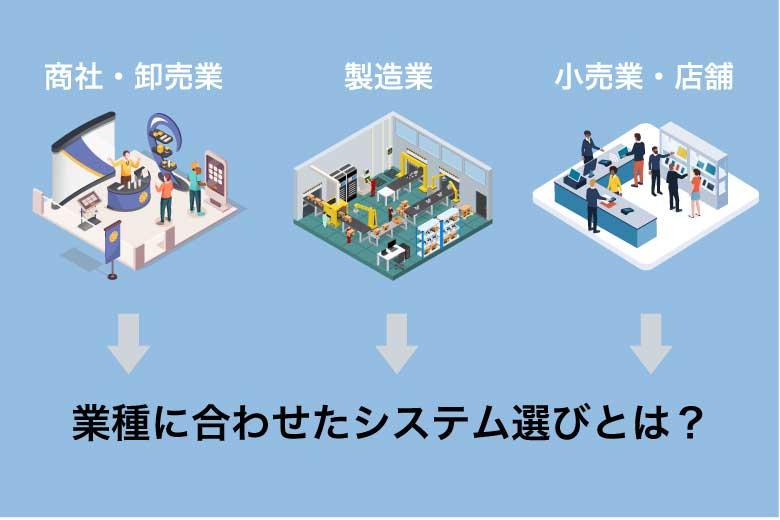
受発注業務の課題やフローは、業界や企業のビジネスモデルによって大きく異なります。
「在庫の回転が早い業種」「オプションが複雑な製品を扱う業種」「発注担当が専門職でない現場」など、現場の特性に応じて適したシステムタイプも変わってきます。
この章では、代表的な業界ごとにおすすめのシステムタイプを整理しながら、それぞれの業種に合った選び方のヒントを紹介します。
4-1. 商社・卸売業:在庫管理がカギ→在庫連携型がおすすめ
商社や卸売業では、多品種・多拠点を扱うケースが多く、「いまどこに、何が、どれだけあるか」という在庫情報の管理が業務の要になります。
もし受注を受けた後に「在庫切れでした」ということになれば、取引先の信用に大きく関わります。
そのため、在庫管理システムや倉庫データと連携できる受発注システムを選ぶことが重要です。
リアルタイムに在庫を確認しながら注文を受けられる仕組みがあると、売り逃しを防ぎつつ、在庫過多のリスクも抑えられます。
| 📌おすすめタイプ:パッケージ型+在庫連携オプション |
4-2. 製造業:仕様・オプションの複雑さに対応→カスタマイズ可能型がおすすめ
製造業では、同じ商品でも「仕様変更」「追加オプション」「納期指定」など、取引先ごとの要望が多岐にわたります。
たとえば、製品Aに対して「A-01」「A-01改」「A-01改(左利き仕様)」のように細かな差分管理が必要になることもあります。
このような業務では、項目の自由設定や入力画面のカスタマイズができる受発注システムでなければ、現場が混乱してしまいます。
既存のシステムではカバーしきれないルールや承認フローがある場合は、ベースのシステムに手を加えられるカスタマイズ開発型を選ぶのが賢明です。
| 📌おすすめタイプ:カスタマイズ開発型 |
4-3. 小売業・店舗チェーン:発注担当のITスキルに配慮→シンプルUI型がおすすめ
チェーン展開する小売店やフランチャイズでは、各店舗からの商品発注を本部が一括で受ける運用スタイルが一般的です。
ただし、店舗側の担当者は必ずしもシステムに詳しいわけではなく、「毎回の発注が面倒」「操作が難しい」と感じてしまうと、定着が難しくなります。
こうしたケースでは、ログイン〜商品選択〜発注完了までの流れが簡潔で、マニュアル不要でも操作できるUI設計が重要です。
スマートフォンやタブレットからも使えるクラウド型を選ぶと、現場への浸透も早くなります。
| 📌おすすめタイプ:パッケージ型(シンプルUI・モバイル対応重視) |
このように、同じ「受発注業務」でも業界によって優先すべきポイントが異なるため、導入するシステムのタイプも柔軟に選ぶ必要があります。
すでにいくつかのサービスを比較している企業でも、「うちの業界には、どれが合うのか?」という視点を持つことで、選定の軸がより明確になるはずです。
次章では、こうした選び方を踏まえつつ、導入時によくある失敗例とその回避法を紹介していきます。
特に、「機能は良いけれど使われない」という状態にならないための注意点を掘り下げていきます。
5.「導入したけど使われない」を防ぐために

受発注システムを導入した企業の中には、「せっかくコストをかけたのに、思ったほど使われていない」「現場から不満の声が上がっている」といった悩みを抱えているところも少なくありません。
こうしたケースでは、システムの機能そのものよりも、「導入の進め方」や「選定時の視点」が結果に大きく影響していることもあります。
この章では、導入時によくある失敗パターンを3つ紹介しながら、事前に避けるためのポイントを解説します。
どのタイプを選ぶにしても、これらをおさえることが「自社におすすめ」のシステム選定のポイントです。
5-1. 失敗1:「多機能すぎて、結局使いこなせない」
システム選定時に「機能が豊富でおトクに見える」「あとで使えるかもしれないから入れておこう」と多機能な製品を選びすぎると、導入後に現場での混乱を招く原因になることも。
とくに、発注や在庫確認などの操作を行うのが営業職や非IT系のスタッフである場合、日常的に使う機能がすぐに見つからない、操作が複雑で覚えづらいといった問題が発生しがちです。
✅対策ポイント 「現場で日常的に使う機能」を軸に設計されているか、操作がシンプルであるかを重視しましょう。 |
5-2. 失敗2:「取引先が使ってくれない」
自社で導入を決めても、実際に注文するのは取引先側——そのため、取引先にとって使いやすく、受け入れられる設計かどうかが成功のカギを握ります。
よくあるのが、「うちはFAXで慣れているから」「新しいシステムは面倒くさい」といった声があがり、結局使われないというパターン。
ITリテラシーが高くない業界では、「誰でも迷わず使える」ことが最優先です。
✅対策ポイント 取引先に向けた操作説明書やサポート窓口の整備、シンプルなログイン方法、スマホ対応などを意識しましょう。 |
5-3. 失敗3:「導入して終わり」になってしまう
システムは入れて終わりではなく、「使い続けられる仕組み」こそが重要です。
社内に十分な説明がなかったり、導入直後にトラブル対応ができなかったりすると、現場から「面倒」「結局アナログでやるほうが早い」という声が出てしまい、活用されなくなってしまうことがあります。
✅対策ポイント 導入後の社内説明会、マニュアル整備、問い合わせ対応の仕組みをあらかじめ準備しておきましょう。 |
【受発注システム選びを失敗しないためのチェックリスト】
チェック項目 | 確認のポイント | チェック ✔ |
操作性はシンプルか? | 現場や取引先が迷わず使えるUIか、よく使う機能がすぐ見つかるか | □ |
必要な機能から始められるか? | 段階導入・スモールスタートが可能か、後から機能拡張できるか | □ |
取引先のITリテラシーに対応しているか? | FAX文化やITに不慣れな企業にも配慮されているか | □ |
スマホ・タブレット対応か? | 外出先・現場からも操作できるか、モバイルでの利便性があるか | □ |
導入サポートがあるか? | ベンダーからの初期設定支援、マニュアル、説明会などがあるか | □ |
運用サポートは十分か? | 導入後の問い合わせ対応、運用トラブル時のサポート体制があるか | □ |
拡張性はあるか? | 他システム(ERP/CRMなど)との連携や他部署展開が見込めるか | □ |
✅ チェックリスト活用アドバイス このチェックリストは、システム導入前の社内検討会やベンダーとの打ち合わせ時に活用するとよいでしょう。 |
次章では、こうした導入課題を踏まえたうえで、現場目線のシンプルさと拡張性を両立したBtoB受発注システム「WONDERCART」をご紹介します。
6.現場と取引先にやさしい、BtoB受発注システム「WONDERCART」
ここまで、受発注システムの基本や選定のポイント、業界ごとの違い、導入時の注意点を見てきました。
とはいえ、自社に合うシステムを探しているものの、「なかなか理想通りの製品が見つからない」「現場や取引先のことを本当に考えた設計なのか不安」——そんな声も多く聞かれます。
そこで本章では、BtoB業務に特化し、現場の使いやすさと取引先への配慮を両立した受発注システム「WONDERCART(ワンダーカート)」をご紹介します。
実際の導入シーンをイメージしやすいように、WONDERCARTの特長をいくつかの視点で整理しました。
6-1. 現場目線で設計された「わかりやすさ」
WONDERCARTは、BtoB向けカタログや販促ツールを数多く手がけてきた新日本印刷が、顧客企業の受発注業務に関する課題を解決するために開発したシステムです。
日々の商材管理や注文対応に悩むお客様の声を受け、「誰でも迷わず使える」「運用が続けやすい」ことを第一に設計されています。
特に意識されているのが、現場でのストレスを減らすためのわかりやすさです。
- よく使う操作はトップ画面に集約
- スマートフォンやタブレットからの操作にも対応
- 初回でも迷わず発注できる画面構成
といった工夫により、ITに不慣れな方でも使いやすく、現場での活用が自然と進みやすいつくりになっています。
6-2. 導入に必要なコンテンツ制作もおまかせ

WONDERCARTは、システムの提供だけでなく、立ち上げに必要なコンテンツ制作まで含めてサポートしているのも、大きな特長のひとつです。
とくに、「商品情報が整っていない」「どこから手をつければいいか分からない」といった状態からでも、スムーズな導入が叶います。
- 一部の取引先・商材だけのスモールスタートにも対応
- 商品マスタの整備やカテゴリ分類もサポート
- 商品撮影や画像加工もプロにおまかせ
- UIや画面デザインのカスタマイズも柔軟に対応
- カタログとシステムの同時制作でコストメリットも
WONDERCARTなら、受発注システムの導入と、必要なコンテンツ制作の両方をワンストップで進められます。
「導入前の準備が大変そう」というハードルを、まるごと引き受けられる仕組みです。
6-3. 取引先に合わせた柔軟な商品表示
WONDERCARTの大きな強みのひとつが、取引先ごとに「見せる商品」を設定できる機能です。
- A社にはAブランドのみ、B社にはBとCの混合など
- 商品の価格・在庫数も個別にコントロール可能
- 商品の非表示設定・グループ単位の管理にも対応
これにより、取引先にとって「関係のない商品が表示されない」使いやすい画面を提供でき、利用率の向上や問い合わせ対応の削減につながります。
6-4. 基幹システムなど外部システムとの連携もスムーズ
日々の受注データをスムーズに社内業務に活かすには、外部システムとの連携が欠かせません。
WONDERCARTでは、以下のような連携が可能です。
- 基幹システムへのCSVエクスポート/インポート
- API連携による商品マスタの自動更新
- 会計・在庫・生産管理システムとの連携実績あり
「品番が変更された」「一部商品が廃番になった」という場合にも、CSVで一括登録できるので、更新の手間も最小限に抑えられます。
WONDERCARTは、パッケージ型の導入しやすさと、カスタマイズ型の柔軟性をあわせ持つ、「ハイブリッド型」の受発注システムです。
現場の負担を減らし、取引先にも使ってもらえる——そんな使われる受発注システムをお探しなら、ぜひ一度資料をご覧ください。
7.まとめ:「受発注システムおすすめタイプ」の選び方とは?
受発注システムの導入は、単なる業務効率化にとどまらず、取引先との信頼関係や企業全体の競争力にも関わる重要な取り組みです。
本記事では、以下のような観点から、受発注システムの選び方について整理してきました。
- 受発注システムの基本機能と導入メリット
- パッケージ型/カスタマイズ開発型/フルスクラッチ型という3つのシステムタイプ
- 業界や商材ごとの選定視点
- よくある導入失敗パターンとその回避ポイント
- 現場と取引先の使いやすさを両立したWONDERCARTの特長
【この記事のポイント】
- 「おすすめ」は自社の課題に合うかどうかで決まる
- 業種・業務フロー・取引先の特徴を見極める
- 現場や取引先が迷わず使えるかが重要
- スモールスタートや将来の拡張性もチェック
すでに受発注システムの導入を検討している方は、まず「自社の業務にとって何が一番の課題か」を整理するところから始めてみてください。
受発注システムには多種多様なサービスがありますが、知名度やランキングだけでなく、自社に必要な機能と対応があるかを見極めることが重要です。
そして、「現場にやさしく、取引先にもやさしい」仕組みをお探しであれば、WONDERCARTの資料もぜひ参考にしてみてください。

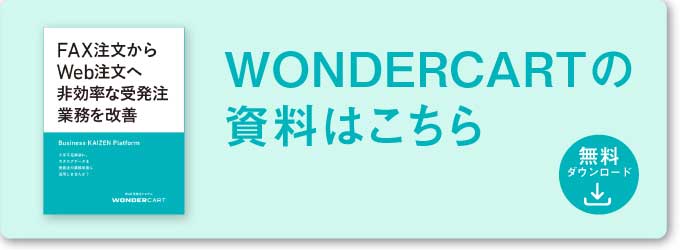

コメント